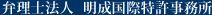トピックス
主張
何度かここでも書いているように、夜、子どもたちと寝る前に、本を読み聞かせています(こちら又はこちら)。
近頃は、子どもらも絵が少ない本も好むようになってきて、最近のお気に入りは、「れいぞうこのなつやすみ」(作:村上しいこ、絵:長谷川義史)をはじめとする「「わがままおやすみ」シリーズ」です。私もお気に入りです。主人公の男の子(小学2年生)は「けんいち」くんですし。私は、関西弁はそこそこしゃべれるバイリンガルなので(むしろ、尾張弁よりもしゃべれるかもしれません。標準語が共通言語だった新興住宅地で18歳まで育ったので)、ちゃんと関西弁で読み聞かせています。
しかし、絵が少ないと言うことは、読むところが多い、ということであり、読み終わるまでに時間が掛かります。そこで、たいていは、「1人のリクエストで、この本の半分までだよ。」ということにして読んでいます。結局、全部読んでしまうことも多いですが。
先日、上の子と下の子が両方そろって、「とびばこのひるやすみ」がいいというので、それを最後まで読み聞かせたところ、読み終わってから、下の娘(6歳)が「やっぱりかえる。」といいだして、「じてんしゃのほねやすみ」をリクエストしました。
そこで、「ダメだよ。二人が「とびばこのひるやすみ」がいいっていったから、これを最後まで読んだんじゃん。一人分なら途中までだよ。」というと、下の娘は、以下のような主張をしました。
a1.おとうさんは、まえに、ルールは、いってからあとのことにしかつかえない(法の不遡及)、といった。
a2.きょうは、「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」とは、いっていない。
a3.ルールは、いってからあとのことにしかつかえない、といったのはおとうさんであるから、おとうさんはそれをまもらなくちゃいけない(禁反言)。
むう。なかなか筋道だった主張をするではないか。「法の不遡及」と「禁反言」を持ち出して自分の意見を主張するとは、幼稚園児にしてはなかなかやるな、と思いましたが、こちらとしても反論はあります。
ca1.「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」というルールは毎日、宣言しなければならないわけではない。
ca2.「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」というルールは、これまで何度も宣言され、実行されてきているので、不意打ちではない。
ca3.ただし、例外的に「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」というルールを不適用として、「ひとりぶんでほんのさいごまで」読んだことは、何度かあることは認める。
ということで、この後の争点は、
I.これまでに、「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」読んだことも、
「ひとりぶんでほんのさいごまで」読んだこともある、という事実がある中で、
「ひとりぶんでほんのとちゅうまで」が原則であり、
「ひとりぶんでほんのさいごまで」が例外であることが、
共通認識としてあったか?
という点になるわけですが、ここは、上記の議論をして子どものアタマの中をぐちゃぐちゃにする(その結果「わからない。」となる)よりは、クリアで筋道だった主張ができたことをほめて、「今回は、自分の意見を上手に言えた」ということを印象づけるべきであろう、と判断し、「うむ。なかなか筋道だった主張をするではないか。では、今日は、チビの要望を容れて、もう一冊、読むことにしよう。」と、「じてんしゃのほねやすみ」も読み聞かせました。
この「「わがままおやすみ」シリーズ」、個人的には、やはり、第1作の「れいぞうこのなつやすみ」がいちばん好きです。夏の屋外プールの感じがよく描かれていて、おすすめです。[ K.H ]
投稿日:2024年10月01日