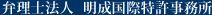トピックス
弊所における生成AIに対する取り組み
昨今、この業界においても生成AIに関するセミナーが多く開催されるようになり、また、生成AIを利用した知財サービスを展開する会社も増えています。既に生成AIの利用を開始した企業・事務所も多くあると思います。
今年に入り、弊所でも、弁理士のMYZKさんが中心となってワーキンググリープを結成し、生成AIについて検討を行いました。ワーキンググループでは、新規検討グループ、中間検討グループ、その他グループと、3つのグループに分かれて、それぞれ、新規出願業務、中間処理業務、その他の業務について、弊所において生成AIがどのように利用可能かを検討しました。生成AIとしては、ChatGPTだけではなく、NotebookLM(Gemini)や、知財ベンチャーが開発したAIアシスタントの試用版など、様々なツールを用いて検討を行いました。
その結果を踏まえ、弊所では、8月1日に、「生成AI利用規程」を策定し、まず、主に中間処理から利用を開始していくことにしました。生成AIの利用を当面控えるという選択も可能だったかもしれませんが、弊所としては、生成AIを避けて通るのは不可能なタイミングまで来ていると判断しました。
ただし、だれでも生成AIを利用できるようにしたわけではなく、一定期間、経験を積んだ弁理士から利用を開始していくことにしました。本願発明および引用発明を適切に捉え、阻害要因等を検討しつつ、そもそも補正が必要かどうか、拒絶理由が論理的に誤りではないか、など、これまで弁理士が経験的に行ってきた作業は、まだまだ生成AIに頼ることはできないと考えており、そのような能力は、ある程度、泥臭い経験が必要だと考えています。最新のAIを使えば引例との差別化のための補正案を提案してくれますが、その補正案が妥当かどうかは、経験を積んだ者でなければ、判断できないのではないでしょうか。
生成AIの進歩は早く、数ヶ月前にできなかったことが現在ではできるようになったなどということは日常茶飯事のようです。そのため、生成AIの利用法や上述した考え方は、すぐに軌道修正する必要があるかもしれません。弊所では、今後も生成AIの動向に注意し、必要に応じて柔軟に検討していきたいと考えています。[ Yu.I ]
投稿日:2025年08月05日