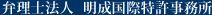トピックス
「発明者」という尊称
昔から本の体裁をしていれば何でも読んできた。小説、随筆、評論、技術書、そして漫画(コミック)。今でも、新聞の書評欄や、新聞の下の方に掲載されている本の広告などを読むのが好きだ。世の中にはこんなに多種多様な本があるのだと思うと、人間の興味の範囲は本当に尽きないと思う。どうしてこんな内容に興味を持ち、本まで書いてしまうのか、と驚くこともあるし、「月刊住職」という月刊誌の広告に気付いて、読者数の上限に思いを致すこともある。この間も、新聞の下に「スゴイ!三角定規付き三角パズル」という本の広告が出ていて、「16種類の三角定規付き」とあった。本の内容より、「いったい16種類って、どんな三角定規だろう」と気になって仕方なかった。
漫画も好きでのべつ読むが、漫画の世界では、少し前から、ライトノベルをコミカライズしたものが増えている。この分野の定番に、異世界転生物がある。広く捉えれば、タイムスリップものもこの範疇に入るだろう。魔法が使える異世界に転生して魔王や魔物と戦う、その際、転生の際に付与されたチートな能力を生かして活躍する、といった話しも沢山あるのだが、最近は、魔力や戦闘力などをチートすることなく、転生する前の知識で、転生後の異世界を生き延びる、そのための苦労や工夫や成功に焦点を当てたものが増えている気がする。
そんなライトノベルのコミカライズものの1つとして、最近、『本好きの下克上』というコミック(4部まであるうちの、第1部と第2部)を読んだ。これは、大の本好きで、本さえ読めるなら幸せという現世の主人公が、虚弱体質の幼女として異世界に転生する話しだ。転生した中世の欧州を思わせる異世界には、本がない。写本はあるが、印刷された本という概念がない、という設定で、本が読めないなら生きていても仕方がない、と思う主人公が、それならいっそ本を作って読もう、と考えるところから、物語は動き出す。しかし体の弱い幼女に転生しているので、簡単にはいかない。知識はある。そこで、周りの手を借りて、パピルスのような物を作ろうとして失敗し、文字を粘土板に残そうとして失敗し、最後は、木の繊維を解(ほぐ)して、漉き、なんとか紙らしいものを作り出す。次は、印刷方法を考える、木版ならできるか、紙を切り抜いたステンシルみたいなものを作れば数枚くらいの印刷はできるのではないか。しかし、印刷を可能とするようなインクはない、黒インクは煤を集めて油で溶けば良いのではないか。印刷機は可能か、幸い異世界の言葉はアルファベットのような表音文字の組み合わせらしく、活字の鋳造ができるのではないか、など、何年も掛けて、少しずつ、本の出版に近づいていく。もちろんそのためには費用がかかるから、主人公は前世の知識を切り売りして金を稼ぐ。例えばできた紙のライセンス料やケーキのレシピの販売などで。さすがに特許制度の仕組みまでライトノベルやコミックで説明し切ることは難しかったらしく、異世界で使えることになっている魔法で独占契約を交わしている。独占を魔法で保証する訳だ。
こうして本のない世界で本を作り出そうとする試みを見ていると、私たちが、電子書籍は言うに及ばず、この数百年、グーテンベルグの発明のおかげで読んできた本というものでも、実に多くの技術の積み重ねによって初めて成り立っているのだと分かる。前世の知識があっても、対応する技術がなければ、直ぐには実現できないのだ。それこそ印刷に適した紙、インク、版などを、全て作っていかなければならない。主人公は、子どもだが、目的に向かって、1つ1つ乗り越えていく、と言うあたりがまぁ読ませどころなんだろうが、第2部までで、こちらの興味が尽きた。
その理由は、この物語の根本もまた1つのチートだから、ということに尽きる。技術の世界では、「できる」と分かっているものを開発するのは比較的たやすい。最も困難で、乗り越えることの難しいものは、できるかどうか分からないものを開発することなのだ。青色発光ダイオードを例に取れば、窒化ガリウムを使えば発光させられるかどうかも分からないなか、多くの人がチャレンジし、後から見れば、発光の寸前まで行った人も少なくなかった筈だ。しかしそこから、残っている最後の壁を破ることは容易ではない。それは、現在地からどの方向に進むのが正しいか、が分からないからだ。そもそも発光は不可能なのかも知れない。何をどう加え、どう処理すれば良いか、無数にある可能性のうちの僅かな組合せが正解である場合、正解を知らない開発者・研究者が、正しい方向に向かって進むのは、それこそ「セレンディピティ(見逃しがちな思いがけない幸運)」をものにするか、あるいはしらみつぶしに、ありとあらゆる可能性を試してみるしかないのだ。正しくできあがった物の存在を予め知っている、ということは、新規な技術の開発者からみれば、チートと言って良いだろう。
私たち、弁理士が相手にしているのは、こうした何が正解か分からない場所で、それでも完成を諦めず、開発を続ける人たちだ。「発明者」という名称は、ないかも知れない正解の前で、なお努力する人への尊称なのだと思う。[ T.S ]
投稿日:2025年04月15日