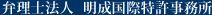トピックス
知財と生成AI
知財業界における生成AIに関する巷の主な関心事項は、生成AIによって生成された成果物の取扱と、生成AIが特許事務所における業務に与える影響にあると感じている。
先日、生成AIを利用して明細書を書いてみる、ことをテーマとするセミナーに出席した。ワークショップ中心で、講師の見解を述べるに過ぎないセミナーとは一線を画しており、現状を肌で感じるには良い機会であった。
世の中的には、簡単なプロンプトを入力して、明細書が完成する流れが念頭に置かれているようであるが、現状は、このような流れには、ほど遠いことを実感した。クレーム作成のセクションでは、予め用意された発明の説明テキストを基に生成AIによってクレームの作成がお題となった。9割方の受講者が、説明テキストをそのまま入力していた。私は、簡単なプロンプト、の観点から、説明テキストから発明の特徴を抽出して、1行程度のプロンプトにて作成を試みた。すると、当たらずとも遠からずのクレームが作成され、正直、少し驚いた。但し、このアプローチは、容易でないと思われる発明の抽出作業を私が実行しており、この作業を、生成AIを用いて確度良く実行することは以下に述べるとおり、容易ではないようである。
一方で、説明テキストを基にする場合、要約基調となる傾向があり、クレーム、という概念からは少し難があるように思えた。講師が示す、工夫を加えたプロンプトを用いた例示では、説明テキストの発明を反映した。かなり洗練されたクレームが作成されていた。と、ここで感じたのは、十分な説明テキストが用意されている事案では有用であるが、十分な説明テキストを用意しなければならない事案では、説明テキストの用意に時間を要し、結局、課題等を明示した明細書レベルのテキストの作成が求められることである。この辺りは、今後改善されるであろうが、やはり、世の中に存在しない発明概念に基づく文書作成はそれほど簡単ではないと感じた。
この感想は、明細書作成のセクションでも同様であり、一般的なシステム構成であっても、頭に思い描く特徴を示すシステム構成を導くにはそれなりの工夫が必要であった。一方で、この点は、同一クライアントの同一技術分野の明細書を用いて生成AIを賢くさせることで順次解決されるとも感じた。
現状、巷で話題となる、生成AIを用いた結果物としての発明については、可能ではあるものの、企業の事業方針を反映した結果物を得ることは容易でなく、どちらかというと、思いもつかなかった視点からの結果物を提案してくれる辺りが現在位置であると認識した。
生成AI領域は生成著しく、1年後、2年後にどのように変化しているのか楽しみである。
[ Yo.I ]
投稿日:2024年09月17日