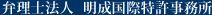電気コネクタ組立体事件
| 判決日 | 2016.07.13 |
|---|
| 担当部 | H27(行ケ)10164 |
|---|
| 発明の名称 | 電気コネクタ組立体 |
|---|
| キーワード | 容易想到性 |
|---|
| 事案の内容 | 無効審判(無効2014-800014号)の無効審決に対する取消訴訟であり、審決が取り消された事案。 引例発明において、溝部49の突出部に対する回転中心突起53の位置が、相手コネクタ33の姿勢の変化に応じたものでないと判断された点がポイント。 <本件発明> 特許第5362136号 |
|---|
事案の内容
【請求項1】
(訂正後クレーム。理解容易のために括弧付き符号を付した。下線は争点に関する箇所を示す。)
ハウジング(11)の周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタ(10)とレセプタクルコネクタ(50)とを有し,嵌合面が側壁面(20)とこれに直角をなし前方に位置する端壁面(15)とで形成されており,ケーブルコネクタ(10)が後方に位置する端壁面(15)をケーブル(C)の延出側としている電気コネクタ組立体において,
ケーブルコネクタ(10)とレセプタクルコネクタ(50)の一方が,平坦面部分を有する突部前縁(21A)と平坦面部分を有する突部後縁(21B)とが前後方向に離間しているロック突部(21)を側壁面(20)に有し,他方が前後方向で該ロック突部(21)に対応する位置で溝部前縁(57A)と溝部後縁(57B)が形成されたロック溝部(57)を側壁面(20)に有し,該ロック溝部(57)には溝部前縁(57A)または溝部後縁(57B)から溝内方へ突出する突出部(59)が設けられており,ケーブルコネクタ(10)は,前方の端壁面(15)に寄った位置で側壁(20)に係止部(22)が設けられ,レセプタクルコネクタ(50)は,前後方向で上記係止部(22)と対応する位置でコネクタ嵌合状態にて該係止部(22)と係止可能な被係止部(60)が側壁に設けられており,上記ロック突部(21)が嵌合方向で上記ロック溝部(57)内に進入してケーブルコネクタ(10)が該ケーブルコネクタ(10)の前端側が持ち上がった上向き傾斜姿勢から嵌合終了の姿勢となったコネクタ嵌合状態では,上記姿勢の変化に応じて上記突出部(59)に対する上記ロック突部(21)の位置が変化することにより,該ケーブルコネクタ(10)が後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,上記ロック突部(21)が上記抜出方向で上記突出部(59)と当接して該ケーブルコネクタ(10)の抜出を阻止するようになっており,該ケーブルコネクタ(10)の前端部には前方へ突出する持上げ部(19)が設けられていて,上記コネクタ嵌合状態で該持上げ部(19)を抜出方向に持ち上げることにより,上記係止部(22)と上記被係止部(60)との係止可能な状態が解除されるとともに,上記ロック突部(21)と上記突出部(59)との上記当接可能な状態が解除されて,上記ケーブルコネクタ(10)の抜出が可能となることを特徴とする電気コネクタ組立体。
【引用発明】(審決認定発明)
ハウジング35とこのハウジング35に設けられた複数のコンタクト37とを有する一方のコネクタ31と
相手ハウジング39とこの相手ハウジング39の内部に設けられた複数の相手コンタクト41とを有し,また,相手ハウジング39の外部から導入されたケーブル44の一端が接続された相手コネクタ33と
を有した回転挿抜コネクタにおいて,
一方のコネクタ31のハウジング35は互いに間隔をおいて対向するよう延出した対の側壁47を有し,これらの側壁47の内面には,溝部49及び係止穴51がそれぞれ形成され,これらの溝部49は,側壁47の延出方向,即ち,コネクタ突合方向の軸線とほぼ直角方向にのびるように形成され,また,溝部49には,中間部分に肩部56及び,該肩部56が形成された面と対向する面から溝内方へ突出する突出部が形成され,このようなハウジング35の対の側壁47の間には,相手コネクタ33の相手ハウジング39が嵌込まれるものであり,さらに,ハウジング35は,上記対の側壁47の内面と直角をなす端部の内面を備え,
相手コネクタ33の相手ハウジング39は,対の側面及びこれと直角をなし,一方のコネクタ31のハウジング35の対の側壁47の間に嵌込まれた際にハウジング35の上記端部の内面に対面する端面を備え,上記対の側面には,それぞれハウジング35の溝部49に嵌込まれる回転中心突起53が形成され,さらに上記対の側面には,一方のコネクタ31のハウジング35の係止穴51に嵌込まれる係止突起60が上記端面に寄った位置に形成され,
相手コネクタ33は,一方のコネクタ31におけるコネクタ突合方向の軸線に対して或る角度を持った状態でその回転中心突起53を溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入され,その後に,相手コネクタ33を反時計方向に回転させ,その結果,相手コネクタ33の係止突起60は,一方のコネクタ31の係止穴51に入り込み回転が停止すると共にロックされ,そして,このロックされた状態において,回転中心突起53は溝部49の上記突出部の下方に位置し,
さらに,相手コネクタ33を一方のコネクタ31から引抜く際には,相手コネクタ33を時計方向に回転した後に,回転中心突起53を溝部49にて案内しつつ上方に引き抜く
回転挿抜コネクタ。
【一致点・相違点】
・一致点(取消事由1:理由無し)
・相違点1(取消事由2:理由無し)
・相違点2(取消事由3:理由有り)
本件発明では,突出部に対するロック突部の位置の変化が,ケーブルコネクタの姿勢の変化に応じたものとされているのに対し,引用発明では,回転中心突起53は,相手コネクタ33は,一方のコネクタ31におけるコネクタ突合方向の軸線に対して或る角度を持った状態でその回転中心突起53を溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入され,その後に,相手コネクタ33を反時計方向に回転させ,その結果,相手コネクタ33の係止突起60は,一方のコネクタ31の係止穴51に入り込み回転が停止すると共にロックされ,そして,このロックされた状態において,回転中心突起53は溝部49の上記突出部の下方に位置するものの,回転中心突起53の位置の変化が相手コネクタ33の姿勢の変化に応じたものとはされていない点。
・相違点3(取消事由4:理由無し)
・相違点4(取消事由5:理由有り)
※本レポートでは、相違点2(取消事由3)についてのみ詳述する。
【裁判所の判断】(判決文P42~P48からの抜粋。下線は担当が付与。)
5 取消事由3(相違点2の判断の誤り)について
(1) 本件審決は,引用発明においても,相手コネクタ33の姿勢の変化に応じて,回転中心突起53は突出部に対する位置が変化するものといえるから,相違点2は実質的な相違点ではない旨判断した。
(2) 引用発明について
しかし,前記3(2)のとおり,引用発明において,相手コネクタ33は,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接している状態(第3図の状態)では,コネクタ突合方向の軸線に対してある角度をもった状態,すなわち,相手コネクタ33の前端側が持ち上がった上向き傾斜姿勢にある状態であり,この状態から相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了状態(第5図の状態)にしているものであるから,引用発明における「回転中心突起53」の位置変化は,回転操作により行われるものではなく,回転操作の前に行われている。したがって,引用発明は,相手コネクタ33の姿勢の変化に応じて,回転中心突起53の溝部49の突出部に対する位置が変化するものであるということはできない。
(3) 相違点2が実質的な相違点であるか否かについて
ア 特許請求の範囲(請求項1)には,本件発明が,①コネクタの嵌合の場面においては,コネクタ嵌合状態では,ケーブルコネクタの姿勢の変化に応じて突出部に対するロック突部の位置が変化することにより,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動されようとしたとき,ロック突部が抜出方向で突出部と当接してケーブルコネクタの抜出を阻止するようになっており,②コネクタの嵌合を解除する場面においては,コネクタ嵌合状態でケーブルコネクタの前端部に設けられた持上げ部を抜出方向に持ち上げることにより,係止部と被係止部との係止可能な状態が解除されるとともに,ロック突部と突出部との当接可能な状態が解除されて,ケーブルコネクタの抜出が可能となるものであることが規定されている。
そして,本件明細書の発明の詳細な説明には,前記1(1)のとおりの記載があり,【0040】には,「ケーブルコネクタ10を意図的に抜出するときには,ケーブルコネクタ10の前端に設けられた持上げ部19に比較的大きな力を上方向に向け作用させる。この力は,…ケーブルコネクタ10を前端側がもち上がる上向き姿勢にもたらす。この姿勢は,図3(B)における実線の姿勢と同じであり,ロック突部21は突出部59と干渉することがなくロック溝部57の外部へ上昇でき,ケーブルコネクタ10の抜出が可能となる。」と記載されている。
そうすると,本件発明は,嵌合では,ケーブルコネクタの前端側が持ち上がった上向き傾斜姿勢から嵌合終了の姿勢への姿勢の変化に応じて,突出部に対するロック突部の位置が変化することにより,ロック突部が抜出方向で突出部と当接してケーブルコネクタの抜出を阻止する一方,嵌合の解除では,ケーブルコネクタの前端側が持ち上がる上向き姿勢となることで,突出部に対するロック突部の位置が元に戻り,ロック突部における抜出方向の突出部との当接が解除され,ロック溝部の外部へ上昇させることによるケーブルコネクタの抜出が可能となるという作用を奏するものであると認められる。
イ これに対し,引用発明は,嵌合の終了姿勢では,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接している状態にあるため,本件発明と同様に抜出を阻止する作用を奏しているものの,嵌合の解除姿勢では,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接されたままであるため,溝部49の突出部の回転中心突起53に対する干渉はなくなっておらず,相手コネクタ33の姿勢を上向き姿勢とするだけでは,相手コネクタ33の抜出はスムーズに行い得ない。
(略)
ウ 以上によれば,本件発明において,相違点2に係る構成は,固有の作用を奏するものであって,単なる設計的事項にすぎないものであるということはできない。
したがって,相違点2は実質的なものである。
(4) 被告の主張について
ア 被告は,引用例には,溝部49に挿入された回転中心突起53は溝部49の中間部分である肩部56で停止すること及びその後,回転中心突起53を反時計方向に回転させてロックさせることのみが記載され,回転中心突起53を右方向に水平移動することや回転中心突起53を中心に円運動することの記述はない,回転中心突起53を右方向に水平移動させ,その後に回転させるとなると,嵌合操作の作業工程として2工程になり,作業効率が低下することから,そのような操作を行うはずがない,などと主張する。
しかし,引用例には,回転中心突起53を支点として反時計回りに回転させると,それに従って,回転中心突起53が,溝部49内を右方向にスライドし,溝部49の突出部の下の位置まで移動するものであることを示す明示的な記載は全くない。
他方,引用例には,「先ず,相手コネクタ33は…或る角度を持った状態でその回転中心突起53をハウジング35の溝部49に挿入される。溝部49に挿入された回転中心突起53は,第3図に示すように,溝部49の中間部分の肩部56で停止する深さまで挿入される。…その後に,相手コネクタ33を反時計方向に回転させる。」と記載されているところ,第3図からは,回転中心突起53が,溝部49の中間部分の肩部56で停止する深さまで挿入され,かつ,右方向への水平移動が終了した状態にあることが見て取れる。
そうすると,引用例には,回転中心突起53を溝部49の中間部分である肩部で停止する深さまで挿入した後右方向に水平移動することについて,明示的な記載はないものの,当業者は,引用発明では,相手コネクタ33を反時計方向に回転させる前に,回転中心突起53の溝部49の肩部56内での右方向への水平移動が行われるものと理解するということができる。
そして,引用例の全体を通じて見ても,回転中心突起53の溝部49の肩部56内での右方向への水平移動の後に,相手コネクタ33の回転が行われるとの理解は,他の記載部分と何ら矛盾しない。被告は,回転中心突起53を右方向に水平移動させ,その後に回転させるとなると,嵌合操作の作業工程として2工程になり,作業効率が低下する旨主張するが,引用例には,回転中心突起53を右方向に水平移動するという操作を省略することによる作業効率の向上については,何らの記載も示唆もないから,引用例の前記記載にもかかわらず,当業者であれば,回転中心突起53を支点として反時計回りに回転させると,それに従って,回転中心突起53が,溝部49内を右方向にスライドし,溝部49の突出部の下の位置まで移動するものであると理解するということはできない。
以上によれば,引用例に,回転中心突起53を支点として反時計回りに回転させると,それに従って,回転中心突起53が,溝部49内を右方向にスライドし,溝部49の突出部の下の位置まで移動するものであること,すなわち,「相手コネクタ33の姿勢変化に応じて」,回転中心突起53が,溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入された位置から溝部49の突出部下方の位置まで突出部に対する位置が移動するものであることが開示されているということはできない。
(略)
ウ 被告は,乙1を見れば,回転中心突起53が肩部で停止した状態となった後,相手コネクタ33を反時計回りに回転させる操作,すなわち,相手コネクタ33を嵌合方向(上方向から下方向)に押し込む操作を行うと,相手コネクタ33は,押し込まれつつスライドするので,いわば滑って倒れるように姿勢が水平方向に変化し,回転中心突起53は肩部56上を略水平に右方向(軸線方向)へ移動して,溝部49の後部である突出部の下方に至り,相手コネクタ33をコネクタ31からコネクタ突合せ方向に直交する溝部方向に動かすことにはなり得ないこと,などを挙げ,引用発明においては,相手コネクタ33を回転中心突起53を支点として反時計回りに回転させると,それに従って,回転中心突起53が溝部内をスライドすると考えるのが自然であり,この場合,回転中心突起が嵌合方向で溝部内に進入した後,嵌合終了時までの間に,相手コネクタ33の姿勢変化に応じて,回転中心突起53は,溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入された位置から溝部49の突出部下方の位置まで突出部に対する位置が移動するものであるから,相違点2は実質的な相違点ではない旨主張する。
しかし,乙1で用いられたサンプル模型と,引用例の第3図や第5図に示されたコネクタとでは,回転中心突起の径と溝部の幅との寸法比率,回転中心突起や溝部が設けられた位置などの点が相当に異なるものである。
よって,乙1から,引用発明において,回転中心突起53が肩部で停止した状態となった後,相手コネクタ33を嵌合方向(上方向から下方向)に押し込む操作を行った場合,相手コネクタ33をコネクタ31からコネクタ突合せ方向に直交する溝部方向に動かすことにはなり得ないなどということはできないし,乙1をもって,引用例の第3図及び第5図を見た当業者が,回転中心突起53を支点として反時計回りに回転させると,それに従って,回転中心突起53が,溝部49内を右方向にスライドし,溝部49の突出部の下の位置まで移動するものであると理解することが裏付けられているということもできない。
したがって,乙1の内容は,前記アの認定を左右しない。
エ 以上によれば,引用発明は,回転中心突起が嵌合方向で溝部内に進入した後,嵌合終了時までの間に,相手コネクタ33の姿勢変化に応じて,回転中心突起53は,溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入された位置から溝部49の突出部下方の位置まで突出部に対する位置が移動するものであるということはできない。
(5) 小括
以上のとおり,相違点2は実質的な相違点であるところ,本件審決には,引用発明において,相違点2に係る本件発明の構成を備えることは容易に想到することができたことは,示されていない。
(略)
したがって,本件審決における相違点2の判断の誤りは,本件審決の結論に影響を及ぼすものである。よって,取消事由3は,理由がある。
【所感】
裁判所の判断は妥当であると思われる。
明細書の記載からは、被告の主張する動作(1工程での挿入完了)も排除していないようにも思える。しかし、被告の主張する動作を採用する積極的な動機付け(作業効率の低下抑制)が明らかでない点、および図面(第3,5図)で表された態様に照らせば、2工程で挿入完了する動作が開示されていると、当業者が理解するとの判断は妥当であると思われる。
裁判所は、図面(第3,5図)の記載に若干重きを置いて、明細書等に開示されている動作を認定しているように感じた。動作を伴う物の発明では、図面の記載が大切であると感じた。