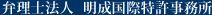豊胸用組成物 損害賠償請求控訴事件
| 判決日 | 2025.03.19 |
|---|
| 事件番号 | R5(ネ)10040 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁特別部 |
|---|
| 発明の名称 | 豊胸用組成物 |
|---|
| キーワード | 産業上利用可能性、調剤行為 |
|---|
| 事案の内容 | 本件は、損害賠償請求控訴事件であり、被控訴人が複数の薬剤を混合して本件発明の技術的範囲に含まれる組成物を製造したとは認められないとした原判決が取り消された事例である。 |
|---|
事案の内容
【事案の概要】
本件は、損害賠償請求控訴事件であり、被控訴人が複数の薬剤を混合して本件発明の技術的範囲に含まれる組成物を製造したとは認められないとした原判決が取り消された事例である。主な争点は、以下の通りである。
・(争点1-2):被控訴人が、本件手術に用いる薬剤として、被施術者に投与する前に、血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(トラフェルミン)及び脂肪乳剤(イントラリポス)という三成分を混合した一の薬剤(組成物)を製造したか。
・(争点1-3):被控訴人は、本件手術の態様として、血漿及び塩基性線維芽細胞増殖因子(トラフェルミン)を含む「A剤」と、脂肪乳剤(イントラリポス)を含む「B剤」とを別々に被施術者に投与していたと主張するが、仮に本件手術がこのような態様であったと認められるとしても、被施術者の体内で「A剤」と「B剤」とが混ざり合うから、被控訴人が「A剤」と「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生産」に当たるか。
・(争点2-1):本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(特許法第29条第1項柱書き)に違反した無効理由があるか。
・(争点3-2):調剤行為の免責規定(特許法第69条第3項)の適用を受けることができるか。
【手続の経緯】
平成24年 2月24日 特許出願(特願2012-38537号)
平成24年 5月30日 拒絶理由通知
平成24年 7月25日 特許請求の範囲を補正
平成24年 8月 9日 拒絶査定
平成24年 9月13日 拒絶査定不服審判請求(不服2012-17926号)
平成24年11月 9日 拒絶理由通知
平成24年11月19日 特許請求の範囲を補正
平成25年 1月 9日 特許審決
平成25年 1月25日 設定登録(特許第5186050号)
令和 4年 3月10日 訴えの提起
【特許請求の範囲】
本件発明(請求項1を引用する請求項4)の内容は、以下の通りである(なお、下線は、審査・拒絶査定不服審判での補正により追加・変更された箇所を示している)。
【請求項1】
自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。
【請求項4】
豊胸のために使用する請求項1~3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。
【原審の判断の概要】
原審は、被控訴人が複数の薬剤を患者に投与したことは認められるものの、被控訴人が複数の薬剤を混合して本件発明の技術的範囲に含まれる薬剤を製造したとは認められないとして、控訴人の請求を棄却した。
【裁判所の判断】
第6 当裁判所の判断
(前略)
2 争点1-2(被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合した組成物を製造したか)について
(1) 認定事実
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
ア 本件クリニックの開設等
医師である被控訴人は、令和元年6月10日、東京都中央区に、診療科目を美容外科及び美容皮膚科とする本件クリニックを開設した。(乙31)
イ 本件手術の提供に向けた準備
(ア) 被控訴人は、令和2年1月頃から、フィブラストスプレー及びイントラリポスを購入し始めた。(乙35、36)
(イ) 被控訴人は、この頃、自らの採取した血液を遠心分離するなどしたほか、厚生労働省の担当者に対して、細胞成分が含まれない血漿を用いた医療サービスの提供が再生医療等の安全性の確保等に関する法律による規制の対象となるかについて照会するなどした。(乙7、8)
(ウ) 被控訴人は、弁理士に対し、仮定した施術方法が本件特許権を侵害しないかについて調査を依頼し、令和2年2月27日付けで、弁理士から本件特許に関する見解書を受領した。その内容は要旨次のとおりであった。(乙32)
a 本件特許は、産業上の利用可能性、進歩性、サポート要件の各要件に違反してされたものであり、無効理由がある。
b 行為A「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離することで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーと、イントラリピッド輸液を混合した組成物(組成物1)を作製する。該患者に対して、豊胸目的で、組成物1を投与する。」は、形式的には本件発明の技術的範囲に属するが、医療行為に該当する実施態様には特許権の効力が及ばないと解されるから、本件特許権を侵害しない。
c 行為B「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離することで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーを混合した組成物(組成物2)を作製する。該患者に対して、豊胸目的で、組成物2とイントラリピッド輸液とを、別々に投与する。」は、組成物2とイントラリピッド輸液の各投与が行われた時点で、本件発明に係る物の生産が行われたと解する余地があるが、人体内部では様々な物質が存在し相互作用していることからすると、組成物2とイントラリピッド輸液とを別々に投与した場合は、本件発明に係るひとまとまりの組成物を投与する場合と同一の効果が得られるとは限らず、本件特許権を侵害しない。
ウ 本件手術の提供
被控訴人は、本件クリニックにおいて、令和2年5月27日から同年11月末頃まではモニター期間としてモニターとして募集した者を対象とし、モニター期間後の同年12月からは一般募集をした者を対象として、いずれも対価を得て本件手術を提供した。(乙45、47、52~58)被控訴人による本件手術は、「自己由来の血漿」を「細胞成分を除いた血漿(NCP)」とし、ヒアルロン酸やプラセンタ等を加えたほかは、本件明細書等に実施例として記載されている方法を用いたものであった。
エ 薬剤ノートの記載
本件クリニックでは、遅くとも令和3年1月27日の本件手術の施術分から、被控訴人が看護師又は准看護師に対し、被施術者に投与する薬剤の各成分量を口頭で指示し、これを受けて、看護師又は准看護師が被施術者に投与する薬剤の成分の内訳等を記載した薬剤ノートを作成し、これに基づいて、看護師又は准看護師は被施術者に使用する薬剤を製造していた。同薬剤ノートには、各行の左端に日付及び被施術者を特定する情報が記載され、各行について、左から「血液」「ガナハ」「フィブラスト」「AAPE」「イントラ」「メルス」「抗」の順に列が設けられ(ただし、令和3年2月23日までの記載においては「抗」の列がない。)、それぞれ数値等が記載されている。また、薬剤ノートの2枚目末尾には、「★ガナハイントラをくだいてまぜた人」との記載があって、被施術者を特定する情報の右に「★」が記載されていることがある。(甲29、乙60、62)
オ 被控訴人が作成した説明資料等
(ア) 本件クリニックのウェブサイトには、本件手術について、「無細胞プラズマジェル」、「カップ吸引固定」及び「バウンド強化EMS」の三つの手順による「3WAY血液豊胸」である旨が紹介され、「注入薬剤」については「術後のしぼみのリスクを回避するため、当院では無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤を組み合わせております。」と記載されていた。(甲3、4、9)
(イ) 被控訴人が、被施術者に交付して署名を求めていた「注入式豊胸手術承諾書および申込書(誓約書)」には、「自己の血液を200ccあるいは400cc採取し、血球成分を除去したものをジェル化し、胸に戻し豊胸する手術です。」、「充填剤として成長因子と一部ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」、「今回の手術で注入できるのは片側100ccあるいは200cc、両側併せて200ccあるいは400ccです。」、「乳房再生豊胸ではトラフェルミン○Rを使用しますが、この薬剤に含まれるエデト酸によるアレルギーがあります。また、イントラリポスには大豆蛋白質は含まれていませんが、卵黄からの脂質が含まれ、アレルギーを起こすことが知られています。乳房再生豊胸時には薬剤アレルギー、卵アレルギーの問診を行い、乳房再生豊胸溶液注入時には血中酸素分圧を監視して行っています。」などと記載されている。(甲6)
(2) 前記(1)の認定事実によると、①被控訴人の指示により、本件手術の被施術者に投与する薬剤を製造する際に、本件クリニックの看護師又は准看護師によって作成され、その記載に基づいて看護師又は准看護師が実際に薬剤を製造していたと認められる薬剤ノートには、「血液」、「ガナハ」(ヒアルロン酸製剤)、「フィブラスト」、「AAPE」(成長因子を含む製剤)、「イントラ」(イントラリポス)、「メルス」(メルスモンという商品名のプラセンタ剤)、「抗」(抗生物質)と、被施術者に投与された成分の量が記載されているが、被控訴人のいうA剤(「フィブラスト」等)とB剤(「イントラリポス」等)に対応する区別がされていない上、薬剤ノートの2枚目末尾には「★ガナハ イントラをくだいてまぜた人」との記載があって、このような記載は、「ガナハ」や「イントラ」を合わせて薬剤に混ぜることが前提になっているともうかがわれること、②本件クリニックのウェブサイトには、注入薬剤について「無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤を組み合わせております」と記載され、被施術者に交付されていた「注入式豊胸手術承諾書および申込書(誓約書)」にも「充填剤として成長因子と一部ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」等の記載と共に、トラフェルミン及びイントラリポスのアレルギーリスクについての説明があること、他方、いずれの記載においても、薬剤が分けて投与される旨をうかがわせる記載は存在しないことなどが認められる。
これらの点に加え、モニターとして募集していた者を対象としていた期間及び一般募集をした者を対象としていた期間を通じて、被控訴人が本件手術において被施術者に投与した薬剤の内容や投与方法を変更したことをうかがわせる事情が全くないことに照らすと、被控訴人は、これらの期間を通じて、被施術者から採取した血液から血漿を製造し、これにフィブラストスプレー、イントラリポスを含む、薬剤ノートに記載された各成分を全て混合させた薬剤を製造した上で、これを本件手術において被施術者に投与していたと合理的に推認できる。
(3) これに対し、被控訴人は、被控訴人が本件手術に先立ち製造していた薬剤は、NCPと成長因子(トラフェルミン)その他の薬剤を混合した「A剤」と、乳化剤(イントラリポス)や栄養剤等を混合した「B剤」であって、本件手術では、まずA剤を胸の奥の方に投与し、次にB剤を胸の皮膚表面近傍に投与し、更にその中間の区間にA剤、B剤を交互にグラデーション状に投与したなどと主張する。
しかし、前記(2)の説示のとおり判断される上に、被控訴人は、当審で実施した本人尋問において、医師である自身の判断として被施術者に各成分をどの程度使用するかを決定し、これを看護師や准看護師に伝えてA剤及びB剤を製造させ、本件手術に際してこれらの薬剤をどのように管理、使用するかという一連の過程について、具体的、合理的な説明をすることができていない。すなわち、被施術者の属性や体質によって適宜選択されるという成分の選択が薬剤ノートの記載に反映されている箇所を具体的に特定することができず、A剤に含まれる成分とB剤に含まれる成分が混在して薬剤ノートに記載されている点については看護師らが意図なくなぜかそのような順で記載したとし、また、院内での薬剤の呼ばれ方については「A、B」、「血漿、白」、「赤、白」などと質問の中で変遷し、施術の三段階目でA剤とB剤とを臨機応変に投与する際の薬剤の交換方法は、看護師等に指示すると言ったり自分で交換すると言ったりと、具体的状況が判然としない。このような被控訴人本人の供述内容、供述態度に加えて、本件において、被控訴人が看護師又は准看護師に指示して、手術に際してA剤、B剤と薬剤を分けて製造させた上、管理及び使用していたならば、当然に存在すべきといえる、そのことをうかがわせる客観的証拠が提出されていないことに照らすと、被控訴人の供述を採用することはできない。
また、被控訴人は、被控訴人による実験結果(乙12、13)に依拠して、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを被施術者の体外で全て混合すると、薬剤が凝固し、被控訴人の用いる機器では投与できないし、仮にできたとしても施術後にしこりが生じるから、被控訴人は上記成分を被施術者の体外で全て混合してはいないと主張する。
しかし、被控訴人による実験は、採取した血液を遠心分離して上層の画分を医療用バットに投入し、イントラリポスとフィブラストを投入して1分間程度適度に揺らしたというものであり、製造方法や管理条件において、本件明細書の実施例に記載されたものと異なっているし、実際に施術する際のものと同一とも限らない。したがって、被控訴人による実験結果をもって直ちに、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを被施術者の体外で全て混合した場合に薬剤が凝固し、投与自体が困難になるなどと認めることはできない。
(4) 上記(2)及び(3)のとおり、被控訴人は、被施術者から採取した血液から血漿を製造し、これにフィブラストスプレー、イントラリポスを含む、薬剤ノートに記載された各成分を全て混合させた薬剤を製造したと合理的に推認できるところ、被控訴人による主張等を考慮しても、同推認を覆すには至らない。
したがって、被控訴人は、モニターとして募集していた者を対象としていた期間及び一般募集をした者を対象としていた期間を通じて、上記三成分を含む組成物を製造したと認められるところ、同組成物は、豊胸手術である本件手術に用いるために製造されたものであるから、被控訴人は、本件発明の技術的範囲に属する組成物を生産したと認められる。
3 争点2-1(本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条1項柱書き)に違反した無効理由があるか)について
(1) 被控訴人は、本件発明は「豊胸用組成物」に係る発明であるが、これを製造するには医師が被施術者から血液を採取して「自己由来の血漿」を得る必要がある上、製造された組成物は、医師がそのまま被施術者の皮下に投与することが前提となっているから、本件発明は、実質的には、採血、組成物の製造及び投与という連続して行われる一連の行為、すなわち豊胸手術のための方法の発明と異なるものではないとの主張を前提として、医療行為は「産業上利用することができる発明」に当たらないから、本件発明に係る特許は無効とされるべき旨主張する。
(2) 法29条1項柱書きは、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」とするのみで、本件発明のような豊胸のために使用する組成物を含め、人体に投与する物につき、特許の対象から除外する旨を明示的に規定してはいない。
また、昭和50年法律第46号による改正前の法は、「医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ。)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」を、特許を受けることができない発明としていたが(同改正前の法32条2号)、同改正においてこの規定は削除され、人体に投与することが予定されている医薬の発明であっても特許を受け得ることが明確にされたというべきである。
したがって、人体に投与することが予定されていることをもっては、当該「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であって、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。
(3) 次に、本件発明の「自己由来の血漿」は、被施術者から採血をして得て、最終的には被施術者に投与することが予定されているが、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、採血、組成物の製造及び被施術者への投与が、常に一連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえない。むしろ、再生医療や遺伝子治療等の先端医療技術が飛躍的に進歩しつつある近年の状況も踏まえると、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造するなどの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発が寄与するところが大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要性が認められる。
そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない。
(4) 以上によると、本件発明が「産業上利用することができる発明」に当たらないとする被控訴人の主張を採用することはできず、本件発明に係る特許は、法29条1項柱書きの規定に違反してされたものということはできない。したがって、同無効理由の存在により本件特許権を行使することができないとする被控訴人の抗弁には理由がない。
(中略)
7 争点3-2(本件特許権の効力が、調剤行為の免責規定(法69条3項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について
(1) 被控訴人は、本件特許権の効力は、法69条3項の規定により、被控訴人の行為に及ばないと主張する。
(2) 法69条3項は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」を対象とするところ、本件発明に係る組成物は、特許請求の範囲の記載からも明らかなとおり「豊胸のために使用する」ものであって、その豊胸の目的は、本件明細書等の段落【0003】に「女性にとって、容姿の美容の目的で、豊かな乳房を保つことの要望が大きく、そのための豊胸手術は、古くから種々行われてきた。」と記載されているように、主として審美にあるとされている。このような本件明細書等の記載のほか、現在の社会通念に照らしてみても、本件発明に係る組成物は、人の病気の診断、治療、処置又は予防のいずれかを目的とする物と認めることはできない。
(3) これに対し、被控訴人は、本件発明は美容医療に関するところ、美容医療は、身体的特徴の再建、修復又は形成による心身の健康や自尊心の改善に寄与する分野であり、治療並びに身体の構造又は機能に影響を及ぼすものであるとして、本件発明が法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬についての発明」に当たると主張する。
しかし、一般に「病気」とは、「生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象」(甲25:広辞苑(第7版))、「生体がその形態や生理・精神機能に障害を起こし、苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態」(甲26:大辞泉(第1版・増補・新装版))という意味を有する語であって、上記のとおり主として審美を目的とする豊胸手術を要する状態を、そのような一般的な意味における「病気」ということは困難であるし、豊胸用組成物を「人の病気の…治療、処置又は予防のため使用する物」ということも困難である。
また、法69条3項は、昭和50年法律第46号による法改正により、特許を受けることができないとされていた「医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」に関する規定(同改正前の法32条2号)が削除されたことに伴い創設された規定であるところ、その趣旨は、そのような「医薬」の調剤は、医師が、多数の種類の医薬の中から人の病気の治療等のために最も適切な薬効を期待できる医薬を選択し、処方せんを介して薬剤師等に指示して行われるものであり、医療行為の円滑な実施という公益の実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図ることにあると解される。しかるところ、少なくとも本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択については、このような公益を直ちに認めることはできず、上記のとおり一般的な「病気」の語義を離れて、特許権の行使から特にこれを保護すべき実質的理由は見当たらないというべきである。
(4) したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんにより調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、法69条3項の規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。
(中省略)
11 結論
そうすると、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人の原審における1000万円及びこれに対する遅延損害金の請求は理由があるから認容すべきところ、これを棄却した原判決は失当であって、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消して控訴人の上記請求を認容し、また、控訴人の当審における拡張請求も一部理由があってこれを認容すべきであるが、その余の拡張請求には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
なお、本件の審理において、法105条の2の11の規定に基づき、いわゆる第三者意見募集を実施した。裁判所に提出された意見書は、いずれも、医療と特許との関係についての実情を踏まえた貴重な意見を含み、裁判所の審理及び判断に有益なものであった。関係者各位に深く御礼申し上げる。
【所感】
原審の判断とは異なり、被施術者の体外で薬剤が混合されたと認定されたことから、被控訴人の行為が本件特許発明に係る組成物の生産に該当すると判断された(争点1-2)。このため、被施術者の体内で薬剤が混合されたとしたら本件特許発明に係る組成物の生産に該当するのかについての判断は示されなかった(争点1-3)。
一方で、本件特許発明に係る組成物は、病気の治療等のために使用する物ではなく、主に審美目的の豊胸に使用する物であることから、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」(特許法第69条第3項)には該当しないとの判断が示された(争点3-2)。このため、美容医療関係者にとっては、特許権侵害とならないよう、これまで以上に注意が必要となったと考えられる。特許権侵害となるか否かの判断に困った際には、弁理士に相談してほしい。
なお、病気の治療等のために使用する物に該当するか否かに関して、乳癌などの病気により乳房を切除した患者の乳房再建のために使用された場合にはどうなるのか、病気や怪我により胸以外の身体の一部が欠損した患者の欠損部を補うために使用された場合にはどうなるのかなど、まだ判然としない部分があるように感じる。今後の動向に注視したい。