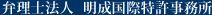自己乳化性の活性物質配合物およびこの配合物の使用事件
| 判決日 | 2016.02.17 |
|---|
| 事件番号 | H26(行ケ)10272 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁第2部 |
|---|
| 発明の名称 | 自己乳化性の活性物質配合物およびこの配合物の使用 |
|---|
| キーワード | 相違点判断の誤り |
|---|
| 事案の内容 | 進歩性(29条2項)を有しないとした審決の取り消しを求めた訴訟。審決には、相違点の判断に誤りがあるとして、審決が取消された。 |
|---|
事案の内容
【手続の経緯】
平成12年5月30日 本件優先日
平成13年5月29日 国際出願(特願2001-587743号(国際公開番号:WO01/91727117881))
平成24年5月 2日 拒絶査定
平成24年9月 6日 不服審判請求
同日 手続補正書を提出
平成24年11月6日 特許を受ける権利の譲渡
平成26年7月30日 「本件審判の請求は、成り立たない」との審決
【請求項1】(補正発明)(下線部が補正部分)
ⅰ)0.1~50重量%の,少なくとも1種の活性物質を含む活性成分,
ⅱ)6~60重量%の,少なくとも1種の脂質を含み,50℃を超えない融点を有する脂質成分,
および
ⅲ)20~93.9重量%の,ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルアルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択される少なくとも1種の結合剤を含む結合剤成分,
を含む自己乳化性固形配合物であって,
前記脂質成分が,12を超えないHLBを有し,
前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず,
前記配合物が,前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み,
前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,
前記配合物。
・活性成分:本発明の目的では,生理学的作用を有するすべての物質を意味する(段落0011)。
・脂質成分: 脂質誘導体および脂質含有混合物をも意味するものである(段落0025)。
・分子分散:物質が,本発明の場合には脂質成分または結合剤成分の少なくとも一部分,好ましくは大部分が,溶媒中に均一に分散されている系を本質的に記述する。そのような場合,溶媒は,通常,マトリックスを形成する。本発明によれば,マトリックスは,結合剤成分または脂質成分によりあるいは少なくとも結合剤成分または脂質成分の大部分により形成される。(段落0042)
・HLB:水と油(水に不溶性の有機化合物)への親和性の程度を表す値。HLB値は0から20までの値を取り、0に近いほど親油性が高く20に近いほど親水性が高くなる。
・自己乳化性:水性媒質に接触する前は固形であるが、水性媒質に接触すると、攪拌等の機械的エネルギーを必要とせずに自発的にエマルジョンが形成される性質。
【審決の理由】
補正発明は,引用文献1(国際公開第00/000179号公報。甲3)に記載された発明(引用発明)及び周知技術に基づいて,本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができ,独立特許要件を満たさないから,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項により本件補正を却下し,本件補正前の請求項1に記載された発明(補正前発明)についても,補正発明と同様の理由により進歩性を欠き,特許を受けることができないから,本件審判請求は成り立たないと判断した。
引用発明の認定
「オイル,脂肪酸またはそれらの混合物に薬物を溶解または分散させ,水溶性ポリマーマトリックスに該溶液または分散物を混合し,混合物を乾燥させた,水難溶性薬物の固体分散製剤において,
脂肪酸が,オレイン酸,リノレン酸,イソプロピルミリスチン酸塩からなる群から選択され,
水溶性マトリックスが,ポリエチレングリコール(PEG),ワックス,ポリビニルピロリドン(PVP)からなる群から選択される,
固体分散製剤。」
(2) 補正発明と引用発明の対比
(一致点)
「ⅰ)少なくとも1 種の活性物質を含む活性成分,
ⅱ)少なくとも1 種の脂質を含む脂質成分,
および
ⅲ)ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルアルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択される少なくとも1 種の結合剤を
含む結合剤成分,
を含む固形配合物であって,
前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,
前記配合物。」
(相違点)
相違点1:補正発明は,各成分の含有量に関し,「ⅰ)0.1~50重量%」の活性成分,「ⅱ)6~60重量%」の脂質成分,および「ⅲ)20~93.9重量%」の結合剤成分とし,さらに,「前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず」と特定しているのに対し,引用発明は上記特定をしていない点。
相違点2:補正発明は,脂質成分に関して,「50℃を超えない融点を有する」とし,かつ,「12を超えないHLBを有し」と特定しているのに対し,引用発明は上記特定をしていない点。
相違点3:補正発明は,配合物を「前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み」と特定しているのに対し,引用発明は,上記特定をしていない点。
相違点4:補正発明は,固形配合物を「自己乳化性」と特定しているのに対し,引用発明は,上記特定をしていない点。
・固体分散体:
固体状態で不活性な担体又はそのマトリックス中に、1種類またはそれ以上の活性成分が分散したもの(W. L. Chiou, S. Riegelman: J. Pharm. Sci., 60, 1281, 1971)と定義されるもの。例えば、薬物と高分子担体を有機溶媒に溶解後、スプレーして乾燥するという単純な操作で容易に固体分散体を製造することが可能。
(参照:www.fujichemical.co.jp/medical/spray_dry/solution/detail.html)
【裁判所の判断】
1 前提事実
(1) 補正発明
補正発明は,上記第2の2に記載のとおりである。この点は当事者間に争いがない。
ア 本願明細書(甲1)には,次のとおりの記載がある。
略
イ 以上によれば,補正発明は,次のとおりの発明であると認められる。
・・・
本件優先日において,乳化された形態で活性物質を利用できることが望まれていたが,製薬技術分野において,活性物質が胃腸管などに適切に吸収されるように低い溶解度の活性物質を製剤化するために用いた,極めて高いHLB値を有するノニオン界面活性剤などの添加剤は,特に高用量では毒性により顕在化するおそれのある欠点を抱えていることが知られており(【0002】~【0006】),また,自己乳化性系と呼ばれている「固体」エマルジョンに用いられる添加剤も,低分子量界面活性剤や高分子グリセリドなどのいずれもHLB値が大きいものであり,これらの配合物の多くは,半固体のコンシステンシーを持つため,ゼラチンカプセル中に充填しなければならない(【0007】)。
そこで,補正発明は,固体の自己乳化性の剤形を提供することを課題とし(【0008】,【0069】),当該課題を解決するための具体的手段として,・・・。
*注:コンシステンシー:含水比により、液状から固体状にまで変化する性質。
(2) 引用発明について
ア 引用文献1(甲3,乙5)には,次のとおりの記載がある。
イ 以上によれば,引用発明は,次のとおりの発明であると認められる。
すなわち,引用発明は,水難溶性薬剤の固体分散製剤に関するものであり,従来,水難溶性薬剤を可溶化し消化液における放出量を増加させる目的で採用された方法,例えば,界面活性剤を使用することによるミセル形成,不活性水溶性担体を使用することによる共沈殿,固体分散などの方法は,溶解性において一定の上昇を示さない,あるいは,半固体又は液体であることから製剤化等に関する欠点が示されていたことから,胃腸管における薬剤の放出を向上させることにより,水難溶性薬剤のバイオアベイラビリティーを改善する固体分散製剤を提供することを目的とし,・・・。
3 取消事由2(相違点判断の誤り)について
(1) 相違点4
まず,審決は,本願明細書の【0001】,【0098】の記載から,配合成分の混合に際し,「溶融により行う」といった手法を採用することにより,「自己乳化性」なる性質は当然に備わると判断し,相違点4は実質的な相違点ではないとした。
しかしながら,上記2(1)で説示したとおり,本件優先日当時,一般には,固体分散製剤と自己乳化性製剤は,水性媒体に接した際に異なる状態となる,別の剤として認識されており,固体分散製剤を溶融混合(溶融法)により製造すれば,自己乳化性製剤となると理解されているわけではない。本願明細書には,自己乳化性固形配合物を製造する方法として,「溶融により行う」ことが記載されているが,固体分散製剤を溶融して製造すれば,必ず自己乳化性を示すと記載されているわけではないのも,同様の認識を示すものと解される。引用文献1の実験Iでも,「水又は人工腸液中における実施例1~10の固体分散製剤2gの懸濁液」と記載されているところ,実施例1~10は,いずれも,薬剤を脂質成分に混合し,溶解又は分散させた後,溶融した水溶性ポリマーマトリックスに組み込み,その後,乾燥させて固体分散製剤を製造しているが,これらの固体分散製剤は,水性媒体に接した際には「懸濁液」となっているのであって,水性媒体に接触すると機械的なエネルギーを付与しなくともエマルジョンとなる自己乳化性製剤ではない。
したがって,固体分散製剤であることと,自己乳化性製剤であることを同視した上記審決の判断は誤りであり,相違点4は実質的な相違点であると認められる。よって,この点に関する審決の容易想到性の判断の当否について,更に検討する必要がある。
(2) 相違点1~4
ア 審決は,脂質成分の選択(相違点2),選択された脂質成分の含有量(相
違点1),製剤中の脂質成分及び結合剤成分の物理的状態(相違点3)と製剤の自己乳化性の有無(相違点4)という4つの点を独立の相違点と評価した上で,引用文献において実施例22でオレイン酸が選択されていることを理由に相違点2を実質的な相違点と認めず,相違点1については,引用文献1における実施例で使用した量と補正発明の相違点に係る量との近さを理由に,相違点3及び4と関連付けることなく容易想到性を肯定し,相違点3についても,溶融押出しを使用すれば水難溶性薬剤成分を分子分散体とでき,その結果得られた製剤は当然に自己乳化性を有するから,相違点4の構成についても想到することができると判断した。
しかしながら,脂質成分の選択及び選択された脂質成分の含有量は,活性物質を十分に溶融させ,最終的にできた製剤中において結晶状態とならないか,他の脂質成分や結合剤成分が分子分散状態で存在できるか否かという点に影響を与える重要な要素と考えられるから,相違点1及び2は,相違点3及び5と無関係に設定できるものではないというべきである。
また,弁論の全趣旨によれば,最終的にできた製剤が分子分散体であるからといって,当然に自己乳化性を示すとは限らず,また,溶融法,溶融押出法のいずれの製法においても,一般的に,溶融時点において分子分散体となっていたからといって,乾燥工程を経て得られた製剤の状態で,なお活性物質が結晶を含まない状態が維持されているとは限らないのであって,その場合には,採用する具体的な条件(成分の種類や含有量,溶融や乾燥の時間,温度等)によって,補正発明の構成に想到できるか否か左右されることになる。そうすると,補正発明の相違点3に係る構成に想到できる条件と相違点4に係る構成に想到できる条件が重なり合うとは限らず,独立に容易想到性を判断すると,ある特定の相違点の構成に想到する条件では,他の相違点の構成に想到できない場合も考えられることになる。
したがって,相違点1~4及び看過した相違点5を同時に達成することが容易に想到できるか否かを検討する必要があるというべきであり,以下,まとめて検討する(上記2で述べたとおり,相違点3と相違点5の容易想到性の判断は重複する。)。
イ 補正発明は,製薬技術分野において,活性物質を胃腸管での吸収性を向上させるという一般的な課題に基づき(【0002】),最終的には,固体の自己乳化
性の剤形(相違点4)を提供することを目的とするものであり(【0008】),配合基剤として,融点が50℃を超えずHLBが12を超えない脂質成分(相違点2)と結合剤成分を含む配合物を選択して,脂肪酸の含有量が「6~60重量%」であり,かつ,「結合剤成分を基準にして40重量%を超え」ない量(相違点1)とし,「前記脂質成分及び前記結合剤成分を含む分子分散体を含」む(相違点3)とした上で,「活性物質の結晶を含まない」(相違点5)ようにしたことは,上記目的を達成するための手段といえる。そして,この場合,固体分散製剤が当然に自己乳化性を示さない以上,引用発明が,相違点1~3及び5の構成を備えれば,当然に相違点4の構成を備えたことになるわけでもない。したがって,相違点1~5の容易想到性については,少なくとも,相違点4に係る構成の容易想到性が肯定されなければ,補正発明の容易想到性を導き出すことができない。
そこで,検討するに,確かに,補正発明の胃腸管での活性物質の吸収性向上という課題は,製薬技術分野において当然の課題であったというべきであり,この点において,補正発明と引用発明は共通するといえるが,活性物質の吸収を高めるための方法としては,本件優先日において,活性成分の粒子自体を小さくする方法に加え,自己乳化性製剤以外に固体分散製剤などの方法があり,吸収性以外の作成難易度等の諸事情を総合的に判断すると,自己乳化性製剤が常に最適であると考えられていたわけではなく,固体分散製剤よりも自己乳化性製剤の方が好ましい等の技術常識はない以上,上記一般的課題から常に補正発明の構成である自己乳化性の剤形を目指すことはできず,何らかの動機付けや示唆がなければ,当業者にとって容易に想到できるものではない。しかるに,引用文献1には,自己乳化性製剤とすることについて記載も示唆もない。
したがって,当業者が,固体分散製剤である引用発明において,脂質成分の選択(相違点2),選択された脂質成分の含有量(相違点1)を設定し,その物理的状態の特定(相違点3,5)を行って,自己乳化性を示す製剤(相違点4)とすることは,容易に想到できる事項とはいえない。
【所感】
判決は妥当であると感じた。
審決においては、相違点4(補正発明は、固形配合物を「自己乳化性」と特定しているのに対し、引用発明は、上記特定をしていない点)に関して、実質的に差異がないもの、又は、当業者が容易になし得るものと判断されているのに対して、この部分が判決では覆っている点が、本件では一番のポイントとなっていると考えられる。
なお、今回の引用文献1は、本願明細書の従来技術として記載されたものであり、発明者らは当然に意識していたと考えられる。
以上