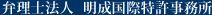脱硫ゴムおよび方法事件
| 判決日 | 2014.07.17 |
|---|
| 事件番号 | H25(行ケ)10245 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁 第1部 |
|---|
| 発明の名称 | 脱硫ゴムおよび方法 |
|---|
| キーワード | 進歩性、用語の解釈 |
|---|
| 事案の内容 | 拒絶査定不服審判の棄却審決に対する審決取消訴訟において、審決が取消されました。 |
|---|
事案の内容
・審決での認定
本願明細書における「脱硫」=引用文献における「脱硫」
・裁判所の認定
本願明細書における「脱硫」≠引用文献における「脱硫」
本願明細書:脱硫=再生
引用文献:脱硫=化学的処理、再生=化学的処理+工学的処理
○本願発明
ゴムの脱硫方法であって,
硫黄架橋している硫黄を含む加硫ゴムを準備する工程と,
前記加硫ゴムをテルピン溶液と接触させて反応混合物を生成する工程を含み,
前記反応混合物には,54~100%の架橋を破壊して,加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量のテルピン溶液が存在している,
前記脱硫方法。
○審決が認定した甲2発明の内容
(甲2:再生ゴムの合理的製造方法」,A,日本ゴム協会誌,1949年,vol.22, No.6, pp. 123-128)
「屑ゴムの脱硫方法であって,
屑ゴムが粗砕きされた後,細く砕かれる工程と,
前記屑ゴムを脱硫罐内に松根油と共に入れて加熱する工程を含み,それにより屑ゴムの脱硫が行われる,
前記脱硫方法。」
注:テルピン油≒松根油
(5) 審決が認定した本願発明と甲2発明の一致点及び相違点
ア 一致点
「ゴムの脱硫方法であって,
硫黄架橋している硫黄を含む加硫ゴムを準備する工程と,
前記加硫ゴムをテレピン溶液と接触させて反応混合物を生成する工程を含み,
反応混合物には,架橋を破壊して,加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量のテレピン溶液が存在している,
前記脱硫方法。」
イ 相違点
本願発明では,「54~100%の」架橋を破壊しているのに対して,甲2発明では,架橋を破壊しているものの,上記「」内の事項の特定がない点。
(6) 相違点に対する審決の判断
甲2発明において,架橋のどのくらいを破壊するかは,再生ゴムの腰の強さ,練りやすさ等の兼ね合いの観点より,当業者が適宜決定する設計事項であるというべきである。
第4 当裁判所の判断
(1) 「脱硫」の語義
本願発明は,上記第2のとおりの「脱硫方法」である。当業界において「脱硫」という技術用語は,一般に,加硫ゴムの網目構造を崩壊させ,ゴム分子の解重合によって可塑性を与えること(甲11,乙2)とされているが,より詳細には,①油13 性溶剤を用いて処理する工程(オイル法,パン法),アルカリ溶液を用いて処理する工程(アルカリ法),中性溶液を用いて処理する工程(中性法)など,加硫ゴムの網目構造崩壊のための化学的処理のみを「脱硫」と称して,その後に可塑性や粘着性を高めるために行うすりつぶしなどの機械的処理(仕上工程,Refining)とは区別し,化学的処理及び機械的処理の両方を行い,再利用可能なゴムにすることを「再生」と称する場合(甲11,甲2),②化学的処理のみならず機械的処理も「脱硫」と称する場合(乙2),③油性溶剤を用いて処理する工程(パン法など)を「化学的再生処理」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「脱硫」又は「脱硫再生」と称する場合(乙4),④化学的処理に用いる溶液を「再生剤」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「再生」と称する場合(甲12)などがある上,行われる処理や条件の違いによってゴムが受ける分子的な変化(硫黄架橋結合の切断とゴム分子主鎖の炭素結合の切断の程度など)が異なる結果,処理後のゴムの性質が異なるものである。
(2) 本願明細書における脱硫
このように,「脱硫」,「脱硫再生」,「再生」の意味する技術的範囲は必ずしも一義的なものではないので,まず,本願明細書における「脱硫」の意味について検討する。
ア 本願明細書においては,「脱硫」について特段の定義はされていないものの,次のとおりの記載がある。
(略)
イ 「脱硫」に関する上記の記載された内容を検討すると,①いずれの実施例においても,1.01×105パスカルよりもやや低い圧力で加硫ゴムをテレピン溶液と共に加熱する「脱硫操作」が行われるのみで,機械的処理等追加の処理は行われておらず,特に,実施例1及び2では「脱硫操作」により「硫黄架橋の結合の分解が基本的に終了した」とされていること,②本願発明の方法で処理したゴムを「脱硫再生ゴム」(段落【0033】)と称していること,及び③背景技術の項において,「脱硫することによってリサイクルする」(段落【0002】),「脱硫の形態に再生する」(段落【0003】),及び「ゴムを再生する様々な脱硫方法」(段落【0004】)といった,「脱硫」と「再生」を区別せずに使用した表現があることによれば,本願明細書では,「脱硫」を「再生」と同義,すなわち,使用済みの加硫ゴムを再利用できる程度の可塑性及び粘着性を有する状態まで処理するという意味で用いているものと認められ,本願発明の「脱硫方法」も,そのような処理を行う方法であると解される。
(3) 甲2発明における脱硫
ア 引用文献には,「脱硫」に関して,次のとおりの記載がある(一部の漢字の書体を変更した。)。
(略)
イ 引用文献の上記記載のうち,特に,「脱硫後の粒子の潰し作業を或る工場ではGrindingと稱し或る工場ではRefiningと稱している。」,「脱硫後の潰し作業をRefining(精細)と呼び判然區別することゝなつたから之に一定せられることを希望する。」,「Refiningは前述の如く脱硫操作後の屑ゴム粒子をロールで更に細かく摺りつぶして可塑性と粘着性を一層附與する作業を云う。」,「我が國では再生ゴム本来の性質は單に脱硫操作のみで得られるものと誤認しRefiningは只脱硫した屑ゴムの取纏めにのみ役立つものなりとして之に重きを置かないものが甚だ多い。」,「再生は脱硫のみならずRefiningに依つても行われるものであり」,及び「3)脱硫 油法の脱硫剤としては現在専ら松根油及び松根タールが,用いられているが之は合成ゴムの再生にも最も有効である。」から見て,引用文献では,松根油などの脱硫剤を用いた脱硫罐内での化学的処理のみを「脱硫」と称し,「脱硫」後にRefiningを行って再利用可能な程度の可塑性及び粘着性を有する形態のゴムを得ることを「再生」と称していると認められる。
(略)
(4) 甲2発明の認定と本願発明との対比
ア 上記のとおり,本願では,「脱硫」を使用済みの加硫ゴムを再利用できる形態まで処理するという意味で用いているものと認められる。したがって,「脱硫方法」である本願発明と対比するために引用文献から認定される甲2発明は,引用文献でいうところの「脱硫」ではなく「再生」の方法であるべきで,本願発明と対比する際に認定されるべき甲2発明は,「屑ゴムの再生方法であって,硫黄架橋している硫黄を含む加硫ゴムである屑ゴムをCracking(粗砕)及びGrinding(細砕)する工程,脱硫罐内に松根油と共に入れて加熱する工程,Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程,を含む屑ゴムの再生方法。」というべきものである。
審決は,引用文献から,屑ゴムを砕き,化学処理する工程までの「脱硫」方法を認定したに留まり,再利用可能な可塑性及び粘着性を有するゴムを得るための「再生」方法全体を認定しなかった点で誤りである。
イ 本願発明の「テルピン溶液」は甲2発明の「松根油」に相当し,本願発明の「脱硫」は甲2発明の「再生」に相当するので,両者は,①甲2発明においては,「Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を含むのに対して,本願発明ではそのような工程を含むことが特定されていない点,②用いるテルピン溶液が,本願発明では54~100%の架橋を破壊して,加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量であるのに対して,甲2発明では量について特定がない点,及び,③本願発明では,「54~100%の」架橋を破壊しているのに対して,甲2発明では,架橋を破壊しているものの,架橋の破壊の程度について特定がない点,において相違する。
したがって,審決の相違点の認定には誤りがある。
2 取消事由4(本願発明の容易想到性判断の誤り)について
(1) 上記1(4)のとおり,本願発明と甲2発明との間には審決の認定しなかった相違点があるので,その点の容易想到性について検討する。
(2) 引用文献においては,「Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」については,「再生は脱硫のみならずRefiningに依つても行われる」,「(Refiningを)をおろそかにしている工場の殆ど總ては・・・出来上つた再生ゴムは粒子が粗く著しい見劣りが感ぜられた」,「何れにしてもRefiningは斯くの如く重要なもの」等とされており,「Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を重視すべきことが強調されている(甲2)。そうすると甲2発明に接した当業者は,再生(本願発明の「脱硫」)に際して「Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を強化するべきことを想到するとしても,「Refining(精細)して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を必須としない構成については,これを容易に想到し得ない。
(3) 本願発明の「54~100%の架橋を破壊して,加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量のテルピン溶液」とは,本願発明の意味での「脱硫」,すなわち,使用済みの加硫ゴムを再利用できる形態まで「再生」すること,を基本的に完了するに足りる量のテルピン溶液を意味すると解される。
一方,甲2発明の「再生方法」では,松根油と共に加熱する工程のみならず,可塑性及び粘着性を強めるRefining工程も必須であって,松根油と共に加熱する工程のみで「再生」が行われるわけではないから,松根油の量は,加硫ゴムを再利用できる可塑性及び粘着性を有する形態まで「再生」するのに十分な量であるとは認められない。むしろ,引用文献には,前記のとおり油の量を多くし加熱時間を長くすると再生ゴムの腰が弱くなるので,そうせずにRefiningを十分に行うことで十分な可塑性と粘着性を有し,腰の強い再生ゴムが得られる旨が記載されているので,油の量を多くすることには阻害要因があるというべきである。
(4) したがって,本願発明と甲2発明との間の上記各相違点に係る構成は,当業者が容易に想到し得たものであるとはいえないから,審決の容易想到性判断には誤りがある。そして,この誤りは結論に影響を及ぼすものであるから,原告主張の取消事由4は理由がある。
【考察】
本願発明に係る屑ゴムの再生プロセスと引用文献に記載された屑ゴムの再生プロセスとは大きく異なるため、本判決の判断は妥当と考えられる。ただ、当業者間においても、定義のあいまいな言葉は多くあり、引用文献を読む際に、自分の考える定義をその言葉に当てはめて読み進めることは大いにあり得ることである。このため、特に、新規性や進歩性を主張する際は、自分の中の固定概念から疑っていく必要があると感じた。