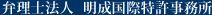包装袋事件
| 判決日 | 2015.1.28 |
|---|
| 事件番号 | H26(行ケ)第10004号 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁 第1部 |
|---|
| 発明の名称 | 包装袋 |
|---|
| キーワード | 引用発明の認定 |
|---|
| 事案の内容 | 本件は、拒絶審決(特願2006-278057号)に対する審決取消訴訟であり,請求が認められずに、審決が維持された事案。原告は、刊行物1に記載された発明を引用発明として認定すべきであることを主張したが、裁判所は、刊行物1の特許請求に係る発明と異なる従来技術として刊行物1に記載された発明も引用発明として認定した。 刊行物1(甲3):国際公開2004/026715号 |
|---|
事案の内容
【請求項1】
積層シートからなる三方シールまたは四方シールの形態にある包装袋であって,積層シートとして少なくとも基材層,バリア層,難開封機能層としての二軸延伸ポリプロピレンフィルム層(OPP),及びシーラント層を含み,易開封機能であるノッチやミシン目加工を施さないことを特徴とする包装袋。(酸素吸収剤層がない)
※なお、括弧書きは、追記
【原告の主張】
審決は,刊行物1発明を「第1積層材料Aからなる周囲をヒートシールされてなる包装袋であって,第1積層材料Aとして基材1a,蒸着層1b,印刷インキ層2,接着層3,二軸延伸ポリプロピレンフィルム層からなる支持体層4,接着層3,及びシーラント層5を含む包装袋。」と認定した。
しかし、刊行物1発明は,「酸素バリア性が高い包装袋」(甲3・1頁5行)を提供するものであるから,酸素吸収剤層を積層させた第2積層材料Bを用いることを必須とし,これを省略することはできない。したがって、酸素吸収剤層を構成として認定していない審決の刊行物1発明の認定は誤りである。
審決は、①「刊行物1発明は,それぞれ別個の積層構造を有する積層シートを用いている包装袋とする点」,②「刊行物1発明は,包装袋を構成する一方の積層シートとして酸素吸収剤層を積層した積層シートを用いることを必須とする点」を看過した。そして,当業者は,これらの相違点にかかる構成を容易に想到することはできないのであるから,審決は相違点の判断も誤ったものである。
【裁判所の判断】
(1)刊行物1発明
確かに,刊行物1の特許請求の範囲の請求項1には,「・・・酸素吸収剤を混入させた合成樹脂からなる酸素吸収剤層,・・・,シーラント層を内面にして重ね合わせ,周囲をヒートシールしてなることを特徴とする包装袋。」と記載されており,刊行物1に主として記載されている発明は,第1積層材料Aのみを用いてシーラント層を内側に重ね合わせ,周囲をヒートシールして構成する包装袋ではない。
しかし,刊行物1には,刊行物1に主として記載された発明の実施例との比較例(従来技術)として酸素吸収剤層を含まない第1積層材料A同士の組み合わせによる包装袋が記載されている(甲3・14頁5行ないし21行)。また,本願の出願前に刊行された特開2005-178149号公報などの複数の文献の記載によれば、同一の積層材料同士を,シーラント層を内面にしてシールして作成した包装袋は,本願出願当時,当業者にとって周知の技術であったと認められる。
審決は,刊行物1の請求項1に記載されている発明を刊行物1発明として認定したものではなく,前記比較例に代表されるような酸素吸収剤層を含まない第1積層材料Aのみを用いてシーラント層を内側に重ね合わせ,周囲をヒートシールすることによる包装袋を刊行物1発明として認定したものと解される。したがって,原告の主張は理由がない。
(2)その他の主張について
(1)で判事したとおり、審決は,刊行物1に記載された従来技術を刊行物1発明として認定したのであるから,刊行物1発明は,包装袋を構成する一方の積層シートとして酸素吸収剤層を積層した積層シートを用いることを必須とする原告の主張は,その前提を欠くものであって理由がない。
(3)なお書き
なお,本件の審理に鑑み,一言付言する。本件は,刊行物1発明の認定が問題となった事案であり,審決は刊行物1に記載されている従来技術を認定したものと解され,原告の主張に理由がないことは前記2で判示したとおりである。しかし,審決は,この点の説示が必ずしも明確でなかったため,本件訴訟にまで至ったものと思われる。審決において,特許公報等の刊行物を用いて引用発明を認定する際に,特許請求の範囲等に記載されている発明自体ではなく,当該刊行物に従来技術として記載されている発明を認定する場合には,当事者に誤解を与えないようにするため,「刊行物には,従来技術として,次の発明が記載されている。」などの表現を用いて,その旨を明示することが望ましい。
【所感】
裁判所の判断は妥当である。従来技術として引用されている文献に記載された技術の全てが、本願の進歩性を判断するための材料として考慮されるのは当たり前であり、裁判所の付言はあるものの、原告の主張が認められることはありえないだろう。ちなみに付言は不要と考える。