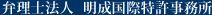リクライニング椅子事件
| 判決日 | 2016.2.23 |
|---|
| 事件番号 | H27(ワ)12748 |
|---|
| 担当部 | 東京地裁 民事第46部 |
|---|
| 発明の名称 | リクライニング椅子 |
|---|
| キーワード | 構成要件充足性 |
|---|
| 事案の内容 | 侵害差止等の請求が棄却された事案。 クレームおよび辞書、並びに明細書および出願経過から導き出される「滑らかに当接して徐々に停止する」の技術的意義に照らせば、被告製品は「滑らかに当接して徐々に停止する」ものではないと判断された。 本件特許権:特許第5255004号 |
|---|
事案の内容
【本件特許】
【請求項1】(太字部分:争点)
1A レッグレストを備え,アームレストの操作によりバックレストを傾倒・起立させるようにしたアームレスト操作式のリクライニング椅子であって,
1B レッグレストフレームと,バックレストフレームと,前記バックレストフレームの下端部に後端部位がピンP4により枢支される座部フレームと,
1C 前脚フレームと後脚フレームの左右上方端部の交差部を枢支してなる脚部と,
1D 後端側をピンP2により前記バックレストフレームに枢支され前端側を上方に回動可能とし,かつ内部に前記交差部を所望の位置に係止可能とした係止部を有するアームレストフレームとを具備し,
1E 前記座部フレームの開放する側の両端部は下方に鈍角状に折り曲げられた湾曲部14cが形成され,該湾曲部の端部には連結棒が取り付けられており,
1F 前記レッグレストフレームが前記座部フレームの前方から引き出し可能であり,
1G 該レッグレストフレームの開放する側の両端部近傍には連結棒が取り付けられ,
1H 連結棒の両端部から突出する先端には,それぞれ当接部材が取り付けられており,
1I 前記レッグレストフレームが引き出される際には,その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑らかに当接して徐々に停止するものである
1J ことを特徴とするリクライニング椅子。
【被告の行為】
ア 被告は,遅くとも平成25年4月26日から,被告製品を譲渡し,又は譲渡の申出をしている。
イ 被告製品のストッパー部材(構成要件1H等にいう当接部材に対応するもの)は,別紙図面(被告製品の取扱説明書中の図面を拡大したもの。甲3の2)のとおり,側面視略L字型である。
【争点】
⑴ 被告製品における構成要件充足性(なお,被告はア及びイ以外の構成要件の充足性を争っていない。)
ア 構成要件1Hの充足性 ⇒判断せず
イ 構成要件1Iの充足性
⑵ 本件特許についての無効理由の有無 ⇒判断せず
【原告の主張】(判決文P5-6)
イ 構成要件1Iの充足性
被告製品は,ストッパー部材が座席フレームの湾曲部に当接し,座席フレームが下方に湾曲するに伴ってストッパー部材も下方へ移動し,その後,ストッパー部材の移動速度が低下して停止しているから,構成要件1Iの「滑らかに当接して徐々に停止する」を充足する。被告は,上記の湾曲部に最初に当接した時点後の行為は本来予定されたものでないと主張するが,上記のとおり,最初に当接した時点ではいまだ最終的に停止する位置に至っていないのであるから,失当である。
【裁判所の判断】(判決文P8-)
第3 当裁判所の判断
1 争点⑴イ(構成要件1Iの充足性)について
⑴ 構成要件1Iにつき,本件発明の特許請求の範囲には,「レッグレストフレーム……の当接部材」が「座席フレームの湾曲部」に「滑らかに当接」して「徐々に停止する」ものであると記載されている。この「滑らか」は,本件明細書(甲1)において定義づけられていないので,「すらすらと通るさま。つかえないさま。よどみないさま」(広辞苑〔第六版〕2103頁),「物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま」(大辞林〔新装第二版〕1924頁)といった意味を有すると解される。また,「徐々に停止する」とは,「徐々に」が「停止」を修飾していることに照らすと,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接すると直ちに停止するのではなく,当接した後も移動を続けつつも次第に減速して停止に至ることを意味すると解される。さらに,「座席フレームの湾曲部」が座席フレームの「開放する側の両端部」にあって「下方に鈍角状に折り曲げられた」構造を有していること(中略)からすれば,レッグレストフレームの当接部材に対しては,引き出す方向に対する抵抗力が次第に大きくなる一方,下方に向かう力がかかっていくと考えられる。
以上を総合考慮すると,「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても直ちに停止することなく更に引き出され続けるが,湾曲部との当接後は湾曲部から受ける力により次第に減速して,当接から多少なりとも間を置いて停止することを意味すると解される。
⑵ この点につき,念のため本件明細書の記載及び本件特許の出願経過を見るに,本件明細書(甲1)においては,「発明を実施するための形態」欄において,円形当接部材が座部フレームの湾曲部の基端部に滑らかに当接すること,及び,鈍角状の上記湾曲部により徐々に停止していくので強く引き出しても衝撃がないことが記載されている(段落【0032】)。また,本件の特許出願について,引用文献(登録実用新案第3046819号公報。乙3)に基づき容易想到であるとする拒絶理由通知(乙2)に対し,原告は,特許請求の範囲(構成要件1I)に「滑らかに」を加える補正をした上,平成25年3月28日付け意見書(乙4)において,本件発明が本件明細書の上記記載のとおりの作用効果を奏するものであり,上記引用文献記載の考案は当接部が屈曲部の下側の曲線部にいきなり当接するもので,滑らかに当接し徐々に停止していくものでは全くないと述べている。
そうすると,構成要件1Iは,レッグレストフレームを引き出した際に衝撃を感じることがないという効果を奏するために,当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても突然停止するのでなく,その後に次第に速度を落として停止することをいうものと解するのが相当であるから,前記⑴の解釈と合致するということができる。
⑶ 以上を前提に被告製品が構成要件1Iを充足するかどうかについて検討するに,証拠(甲9,乙7の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,レッグレストフレームを前方に引き出していくと,同フレームに取り付けられた側面視略L字型のストッパー部材の上端ないし引き出し方向先端の角の部分が座席フレームの湾曲部に当接し,その直後にレッグレストフレームが,次第に減速するのではなく,ほぼ一瞬にして停止するものと認められる。
したがって,被告製品は,「滑らかに当接して徐々に停止する」ものでないから,構成要件1Iを充足しない。
⑷ これに対し,原告は,被告製品においてレッグレストフレームを引き出してストッパー部材が座席フレームの湾曲部に当接した段階で停止するのは最終的な停止でなく,滑らかに当接して徐々に停止する効果は更に引き出して最終的に停止する際に生じると主張する。
そこで検討するに,証拠(甲9,乙8)によれば,被告製品のレッグレストフレームを引き出すと,①座席フレームの湾曲部にレッグレストフレームのストッパー部材が当接して同フレームが停止し,②その後,更にこれを上方に引き上げる操作を行うと,上記部材が上記湾曲部に沿って下方に移動し,徐々に速度を落として停止するものと認められる。この②の動きは「滑らかに」と見る余地があるが,既に①において同フレームのストッパー部材は湾曲部に当接しており,改めて当接が生じるものでないから,被告製品のストッパー部材が「湾曲部に滑らかに当接」するものとはいえない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
【所感】
裁判所の判断は妥当であると考える。
但し、「被告製品を実際に触れていないので分からないが、被告製品においてフットレストの引き出し方によっては、構成要件1Iを充足する場合もあるのではないか」との意見が挙がった。具体的には、被告製品の取扱説明書には、フットレストの取り出しについて「少し上げながら引き出してください」と記載されており、この記載に従って引き出した場合、①の手順と②の手順とが連続して行われて、ストッパー部材が湾曲部に沿って下方に移動し、徐々に速度を落として停止するとも思われる。
なお、裁判所の判断に対して仮に反論するのであれば、以下の内容での反論が想起される。
裁判所は、構成要件1Iの「当接して」について、上述の①、②の手順のうち、「①において既に当接しており、改めて当接が生じるものではない」と述べている。しかし、「滑らかではなく当接して」いる状態から「更に引き出す操作(②の手順)」を行うことで、「滑らかな当接」が生じると捉えれば、②の手順における被告製品の様子は、構成要件1Iを充足するとも考えられる。
但し、証拠(甲9,乙8)によれば、②の手順は、より正確には「更にこれを上方に引き上げる操作」であるようなので、構成要件1Iにおける「前記レッグレストフレームが引き出される際には」とは異なる点を考慮すると、上記内容での反論は容易ではないと思われる。