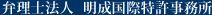ビークル 審決取消請求事件
| 判決日 | 2025.03.24 |
|---|
| 事件番号 | R6(行ケ)10049 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁第3部 |
|---|
| 発明の名称 | ビークル |
|---|
| キーワード | 課題の共通性 |
|---|
| 事案の内容 | 本件は、拒絶査定不服審判の不成立審決に対する取消訴訟である。判決では、引用文献の課題の前提を捨象することは認められないとされ、本件審決は取り消されるべきものであるとされた。 |
|---|
事案の内容
【手続の経緯】
令和 2年 7月20日 本願国際出願日 (特願2021-534025)
令和 5年 1月 4日 拒絶査定
令和 5年 4月12日 拒絶査定不服審判請求
令和 6年 4月10日 拒絶査定不服審判の請求不成立の審決
令和 6年 5月22日 審決取消訴訟の提起
【請求項1】(請求不成立の審決がなされたもの)
ビークルであって、
前記ビークルは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであり、
前記ビークルは、
回転するクランク軸を有し、燃焼によって生じるパワーを前記クランク軸のトルク及び回転速度として出力するエンジンと、
前記クランク軸と連動するよう設けられ前記エンジンに駆動され発電する発電用電動機と、
前記発電用電動機で発電された電力をエネルギーとして貯蔵するエネルギー貯蔵装置と、
前記発電用電動機とは異なる、前記エネルギー貯蔵装置及び/又は前記発電用電動機からの電力の供給を受けてパワーを出力する、推進用電動機と、
前記推進用電動機から出力されたパワーによって駆動される推進器と、
前記エンジンと、前記推進用電動機と、前記発電用電動機とを制御する制御装置であって、加速指示に応じて前記推進用電動機に供給される電力を増大するよう前記エンジン及び前記発電用電動機を制御し、前記推進器が前記推進用電動機から出力されたパワーのみによって駆動される場合、前記エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に関わらずに、前記加速指示を契機として、前記エネルギー貯蔵装置及び/又は前記発電用電動機から供給される電力で駆動される前記推進用電動機により前記加速指示に応じた目標パワーを出力するように、前記加速指示よりも前に、少なくとも前記発電用電動機で発電された電力の供給の受け及び前記推進用電動機に対し電力の供給を行なう前記エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に応じて前記発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速する制御装置と、を備える。
【審決の概要】(以下、判決文の一部を抜粋する。下線は筆者が付したものである。)
・本願と引用文献1(特開2001-211505号)の相違点について
本件補正発明は、「リーン姿勢で旋回可能に構成された」車両又は「ドローン」であるのに対し、引用発明は、そのようなものであるか明らかでなく、また、「制御装置が、推進器が推進用電動機から出力されたパワーのみによって駆動される場合、エネルギー貯蔵装置の供給可能な電力に関わらずに、加速指示を契機として、エネルギー貯蔵装置及び/又は発電用電動機から供給される電力で駆動される推進用電動機により加速指示に応じた目標パワーを出力するように、加速指示よりも前に、少なくとも発電用電動機で発電された電力の供給の受け及び推進用電動機に対し電力の供給を行なうエネルギー貯蔵装置の供給可能な電力に応じて発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速すること」について、本件補正発明は、エネルギー貯蔵装置の「エネルギー貯蔵量に関わらずに」、加速指示を契機として、エネルギー貯蔵装置及び/又は発電用電動機から供給される電力で駆動される推進用電動機により加速指示に応じた目標パワーを出力するように、エネルギー貯蔵装置の「エネルギー貯蔵量に応じて」発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速するものであるのに対し、引用発明は、バッテリ9(エネルギー貯蔵装置)の「バッテリ温度が低く供給可能な電力が低下する場合でも」、アクセルペダルの操作量が増大され(加速指示を契機として)、バッテリ9(エネルギー貯蔵装置)及び/又は発電機2(発電用電動機)から供給される電力(供給される電力)で駆動される電動機4(推進用電動機)によりアクセル操作量APS(加速指示)に応じた駆動出力が得られる(目標パワーを出力する)ように、バッテリ9(エネルギー貯蔵装置)の「バッテリ温度が低く供給可能な電力が低下する場合にはバッテリ温度が低いほど」同じ出力を保ちつつエンジン1及び発電機2の動作点が高回転速度且つ低トルク側へと変更しエンジン1の余裕トルクを増大させる(発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速する)ものである点。
・相違点の容易想到性について
エンジンと電動機とエネルギー貯蔵装置とを備えたビークルの技術分野において、『エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合やエネルギー貯蔵量(SОC)が低下した場合に、エネルギー貯蔵装置の供給可能電力が低下すること。』は、きわめて周知の技術的事項である。
そして、引用発明において、かかる課題を解決するために、駆動力制御装置(制御装置)が、アクセルペダルの操作量が増大されるか否かにかかわらず(加速指示よりも前に)、少なくとも発電機2の発電出力の充電(発電用電動機で発電された電力の供給の受け)及び電動機4に電力を供給する(推進用電動機に対し電力の供給を行なう)バッテリ9(エネルギー貯蔵装置)のバッテリ温度が低く供給可能な電力が低下する場合には、バッテリ温度が低いほど同じ出力を保ちつつエンジン1及び発電機2の動作点が高回転速度且つ低トルク側へと変更し、エンジン1の余裕トルクを増大させる(発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速する)にあたり、供給可能な電力が低下する場合として、周知事項に鑑みて、バッテリ(エネルギー貯蔵装置)温度が低い場合に代えて、あるいは、これに加えて、エネルギー貯蔵量(SOC)が低下した場合を採用し、本件補正発明のように、エネルギー貯蔵装置の『エネルギー貯蔵量に応じて』発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速するように構成することに格別の困難性は認められない。
そうすると、引用発明において、周知技術を考慮に入れ、また、周知事項に鑑みて、相違点に係る本件補正発明の発明特定事項に想到することは当業者が容易になし得るものである。
【裁判所の判断】
引用文献には、「エンジンを低回転かつ高負荷で運転すると、エンジンの余裕トルクが小さくなるため、エンジンの応答性、更には発電機の応答性が低下し、車両の急加速時や補機負荷の急増時に必要な電力を発電機から電動機に供給できない状況が生じる」(段落【0006】)、「このような状況であっても、不足電力分をバッテリから供給できれば加速応答性を損なわない良好な運転性を実現できるのであるが、バッテリ温度が低いとバッテリから供給可能な電力が小さくなって上記加速に必要な電力を供給できず、加速不良を生じてしまう。」(段落【0007】)、「本発明は、上記技術的課題を鑑みてなされたものであり、バッテリの温度が低いときに、バッテリから加速に必要な電力を供給できなくなるのを防止し、良好な加速応答性を確保することである。」(段落【0008】)、「蓄電装置の最大出力は蓄電装置の温度によって決まり、上記不足電力がこの最大出力を上回ると蓄電装置より十分な電力が供給できず、加速不良の原因となってしまうが、本発明を適用することにより、蓄電装置温度が低く最大出力が小さいときは発電出力の応答が早められ、発電出力の応答遅れによる不足電力が常に蓄電装置の最大出力以下に抑えられる。これにより、加速に必要な電力を蓄電装置から十分に補うことができないことによる加速不良が防止され良好な加速応答性を確保することができる。」(段落【0014】)との記載がある(別紙「引用文献の記載」)。引用文献の上記各記載によれば、引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が小さいという課題を解決するものであると認められる。…
引用文献の段落【0039】ないし【0042】は、駆動力制御装置が適用される車両において、発電機2から電動機4に供給される電力が不足すると、バッテリ9から電動機4に不足分の電力が供給されるが、この不足分がその時点におけるバッテリ9の最大出力を超えてしまうと、電動機4へ供給できる電力が不足して駆動に使用できる電力が減少し、加速応答性が低下し、かつ、発電出力の応答はエンジン1の余裕トルクが小さいほど遅くなるという一般的な問題を挙げている。しかし、引用文献は、これに次いで、段落【0043】において、「更に、バッテリ温度が低い時にはバッテリ9の最大出力が低下するため、電動機4へ供給される電力が不足しやすくなる。」とあり、上記のバッテリ温度が低い場合には、前記の一般的な問題に加えて、バッテリ温度が低い場合の特有問題も生じることを指摘しており、「そこで、本発明に係る駆動力制御装置では、バッテリ9の温度を検出し、検出された温度が低いときは同じ出力を保ちつつエンジン1及び電動機2の動作点を高回転速度且つ低トルク側へと変更し、エンジン1の余裕トルクを増大させている。」(段落【0045】)としており、これらの引用文献の記載からも、引用文献はバッテリの温度が低い場合の構成を示すものであると認められる。したがって、引用文献の段落【0040】ないし【0042】及び【0044】の記載や、段落【0043】に「更に」との文言が用いられていることをもって、引用発明の課題が被告の上記主張のとおりの内容であると認めることはできない。そして、本件審決は、「エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合やエネルギー貯蔵量(SOC)が低下した場合に、エネルギー貯蔵装置の供給可能電力が低下すること。」が周知の技術的事項であると認定しているが(本件周知事項)、上記内容が周知の技術的事項であるのであれば、当業者は、エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合、エネルギー貯蔵量が十分(例えば100%)であっても供給可能電力が低下することを認識するといえる。そうすると、当業者は、エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合と、エネルギー貯蔵量が低下した場合とでは、状況が異なると理解するといえ、エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合に対応した構成を、エネルギー貯蔵量が低下した場合に採用する理由があると直ちに認めることはできず、上記構成をエネルギー貯蔵量が低下した場合に採用する理由があることの根拠を本件審決が示しているとも解されない。
以上によれば、引用文献の記載に接した当業者が、引用発明の課題として、「バッテリ温度が低い時に」という前提を捨象して、加速に必要な不足電力分をバッテリから供給できないことによる加速不良を解消し、良好な加速応答性を確保することを認識するとは認められず、被告の上記主張は採用することができない。
【所感】
引用発明の課題の上位概念化を認めなかった裁判所の判断は妥当であると感じた。
拒絶理由通知において、引用発明と特許請求の範囲に係る発明との課題が共通であると認定された場合には、引用発明の課題が過度に上位概念化されていないか検討する必要がある。捨象された内容に引用発明の重要な部分が含まれている場合には、本件のように課題の認定の誤りを指摘し、課題が共通しないことを主張することが考えられる。