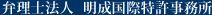エレベータ事件
| 判決日 | 2010.12.28 |
|---|
| 事件番号 | H22(行ケ)10110 |
|---|
| 担当部 | 知財高裁第3部 |
|---|
| 発明の名称 | エレベータおよびエレエータのトラクションシーブ |
|---|
| キーワード | 新規事項、進歩性 |
|---|
| 事案の内容 | 拒絶査定不服審判で進歩性無しとして拒絶審決を受けた出願人が取り消しを求め、請求が認容されて拒絶審決が取り消された事案。 副引用例の技術的課題を考慮すると、本願発明と引用発明との相違点に関する構成に至るために,副引用例の技術を適用することは困難である、と判断した点がポイント。 |
|---|
事案の内容
【経緯】
平成14年 2月25日 PCT出願(特願2002-573347号 (以下、本件特許出願))
平成19年 7月23日 拒絶査定
平成19年10月29日 原告が拒絶査定不服審判請求
平成19年11月26日 補正書提出
平成21年11月25日 審判請求は成り立たない旨の審決(本件審決)
【特許請求の範囲】
【請求項1】(平成19年11月26日付け補正前)<本願発明>
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープ(3)から成る一連の巻上ロープ(3)がカウンタウェイト(2)およびエレベータカー(1)を懸垂し,綱溝(101)を備えた1つ以上の綱車(4,7)を有し,該綱車(4,7)の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブ(7)であり,該トラクションシーブ(7)は駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープ(3)を動かすエレベータにおいて,少なくとも前記トラクションシーブ(7)は前記一連の巻上ロープ(3)と共同して材料のペアを形成し,該材料のペアによって,前記トラクションシーブ(7)の表面の被覆材(102)が失われた後に,前記巻上ロープ(3)は前記トラクションシーブ(7)に食い込むことを特徴とするエレベータ。
【請求項1】(平成19年11月26日付け補正後)<本願補正発明>
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープ(3)から成る一連の巻上ロープ(3)がカウンタウェイト(2)およびエレベータカー(1)を懸垂し,綱溝(101)を備えた1つ以上の綱車(4,7)を有し,該綱車(4,7)の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブ(7)であり,該トラクションシーブ(7)は駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープ(3)を動かすエレベータにおいて,少なくとも前記トラクションシーブ(7)は前記一連の巻上ロープ(3)と共同して材料のペアを形成し,該材料のペアによって,前記トラクションシーブ(7)の表面の被覆材(102)が失われた場合,該トラクションシーブ(7)が前記巻上ロープ(3)によって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープ(3)を把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベータ。
【当裁判所の判断】
(1)新規事項について
『「食い込む」及び「破損」の一般的な意味は,次のとおりである。すなわち,「食い込む」とは,「《1》深く内部に入り込む。《2》他の領域へ入りこんで侵す。侵入する。」ことを意味し(甲16。広辞苑第三版),他方,「破損」とは,「やぶれ損ずること。こわれること。」を意味する(乙1。広辞苑第四版)。
そして,上記(1)(注:上記(1)は本件の当初明細書の段落0006の記載)の「トラクションシーブは,トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。」,「巻上ロープの材料より柔軟で,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため,巻上ロープはその特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。」などの詳細な説明部分を前提とするならば,当初明細書等に記載された「前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込む」とは,せいぜい,巻上げロープがトラクションシーブの内部に,入り込むことを意味するものであって,トラクションシーブを欠損させたり,亀裂を入れたり,傷つけたりするなどの態様で変化させることを含む意味として,説明されていると理解することはできない。そうすると,本願補正において「該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して」と付加変更された部分は,巻上ロープがトラクションシーブを部分的にこわすことを意味し,トラクションシーブが欠損したり,亀裂が入ったり,こわれたりする状態に至ることを含むものと理解すべきであるから,本件補正は,本件補正前の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものというべきである。』
(2)進歩性について
『前記(1)によれば,本願発明は,トラクションシーブの表面の被覆材が破壊されたり,消失したりするような異常事態となっても,エレベータの運転に必要な把持力を一時的に確保するように,材料のペアを形成するものであり,被覆材が破壊ないし消失してトラクションシーブとロープが接触すると,巻上ロープに加わるエレベータとカウンタウェイトの応力により,即時にトラクションシーブが変形し,巻上ロープがその中に食い込むことにより,エレベータの落下事故などを防止することを解決課題とするものであって,その解決のために,第2の2(1)記載の構成を採用した。
他方,前記(2)によれば,引用文献1記載の発明2は,トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合に,巻上ロープがトラクションシーブに入り込んで把持力を確保し,トラクションシーブと巻上ロープが共同して安全確保手段を形成する点では,本願発明と一致しているものの,その構成は,U字形ないしV字形のトラクションシーブ溝の接触部で,くさび効果により,ロープとの強い摩擦力を得ることにより,エレベータの落下事故などを防止するものであって,「材料のペア」及び「即時のトラクションシーブの変形」に関する技術思想の記載又は開示はない。
また,前記(3)によれば,引用文献2記載の技術においては,トラクションシーブの表面に被覆材がなく,トラクションシーブの溝の側面のみが,常にロープと接触する溝形状としたエレベータにおいて,巻上ロープ外層線がシーブとの繰り返し接触により徐々に塑性変形し,表面層が加工硬化してもろくなり,やがて断線に至ることを防止し,より耐摩耗性を高めることを解決課題として,シーブ及びロープの硬度を所定以上のものとする等の構成を採用したものである。
以上のとおり,本願発明は,異常事態が発生した場合に,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませ,シーブとロープとの間に十分な把持力が得られるようにして,エレベータの機能及び信頼性を保証させるものであり,異常事態が発生したときにおける,一時的な把持力の確保を図ることを解決課題とするものである。また,引用文献1記載の発明2も,本願発明と同様に,何らかの原因よって高摩擦材が欠落するような異常事態が生じた場合を想定し,その際,ワイヤロープがU字形またはV字形のトラクションシーブ溝の接触部で接触し,この部分で摩擦力を得ることによって,エレベータ積載荷重を確保させることを解決課題とする発明である。
これに対して,引用文献2記載の技術は,上記のような異常事態が発生した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していない。そうすると,本願発明における引用文献1記載の発明2との相違点に関する構成に至るために,引用文献2記載の技術を適用することは,困難であると解すべきである。』
【感想】
(1)新規事項に該当するという判断は妥当だと思われる。
(2)進歩性については、以下の点で多少の疑問がある。
《1》『引用文献1記載の発明2は,…「材料のペア」及び「即時のトラクションシーブの変形」に関する技術思想の記載又は開示はない。』(前頁23~29行)と認定されているが、このうち、『「即時のトラクションシーブの変形」に関する技術思想の記載又は開示はない』の部分は誤認の疑いがある。第1に、本願発明では「前記巻上ロープ(3)は前記トラクションシーブ(7)に食い込む」と規定されており、「即時のトラクションシーブの変形」を構成要件としていない。これは、本件の図3について、綱溝形状203によってロープを効果的に食い込ませるという説明があることからも裏付けられる。第2に、引例1には、第3図のように高摩擦材11が消失した場合に、ロープ6がトラクションシーブ3のV字溝の接触部14で接触し、この部分で摩擦力を得ることが記載されており、このようにロープ6がトラクションシーブ3のV字溝に嵌り込む形態は、本願発明の「前記巻上ロープ(3)は前記トラクションシーブ(7)に食い込む」に該当すると判断できるのでは無いかと思われる。
《2》上記《1》を考慮すると、本願発明と引例1との相違点は、本願発明は「材料のペア」という限定があるのに対して、引例1では材料についての言及が無い点だけではないか?但し、本願発明では、「該材料のペアによって,前記トラクションシーブ(3)の表面の被覆材(102)が失われた後に,前記巻上ロープ(3)は前記トラクションシーブ(7)に食い込む」と記載されているだけであり、具体的にどのような「材料のペア」であるかは特定されていない。そうとすれば、引例1との相違点は実質的にほとんど無いようにも思われる。
(3)なお、最近の裁判例においては、発明の要旨認定の場面において、原則として明細書及び図面の記載を参酌しないという手法(リパーゼ事件)から、明細書及び図面の記載を参酌してクレームの用語の意味をより限定的に解釈する手法に変化しつつある可能性がある。この点については、今後の裁判例を注意深く見守る必要があると思われる。