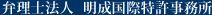シート貼付構造体及びシート貼付構造体を用いて保護シートを貼付する貼付方法審決取消請求事件
| 発明の名称 |
シート貼付構造体及びシート貼付構造体を用いて保護シートを貼付する貼付方法 |
| 事案の内容 |
本件は、特許無効審判の一部無効審決の取り消しを求める審決取消訴訟であり、原告の請求が棄却された事案である。引用例(「大型ディスプレイ」用の光学フィルム)に「延出部」を設けること、および、引用例の「仮止部」を1箇所に特定することに阻害要因はないと判断された。 |
事案の内容
【手続の経緯】
平成24年12月 6日 出願 (特願2012-267651)(優先日 平成24年7月31日)
平成26年 5月23日 設定登録(特許第5547792号)
令和 元年10月10日 無効審判請求(無効2019-800085号)
令和 3年 5月28日 特許請求の範囲について訂正請求
令和 3年 9月22日 一部無効審決
令和 3年10月29日 審決取消訴訟提起
【特許請求の範囲】
【訂正後の請求項1】(以下、本件発明1とも記載)
装置の表面に貼り付けられて前記表面を保護する保護シートであって、接着面を有する保護シートと、
前記接着面を覆うと共に、分離ラインを介して並んで配置される第1剥離部及び第2剥離部を有する剥離シートと、
前記第1剥離部及び前記第2剥離部それぞれから前記保護シートの外側に延びる延出部と、
前記第1剥離部における前記保護シートとは反対側の面に設けられる仮止部であって、前記第1剥離部の外側にはみ出ないように前記第1剥離部に重なって配置され、前記装置に貼り付け可能であって、前記保護シートを前記装置の表面に仮止めするための前記第1剥離部より小さい1箇所の仮止部と、を備えることを特徴とする保護シート貼付用のシート貼付構造体。
(筆者注記:請求項中の下線部は、訂正請求による訂正箇所)
【審決の要旨】
本件発明1と甲3(WO2012/074802)に記載された発明(以下、甲3-1発明とも記載)との間で、以下の相違点が認定された。
<相違点3-1> 本件発明1が「延出部」を有するのに対し、甲3に記載された発明(以下、甲3-1発明とも記載)が「延出部」を有しない点。
<相違点3-2> 本件発明1の仮止部が1箇所であるのに対して、甲3-1発明におけるPSA領域(pressure sensitive adhesive regions)は個数が特定されていない点。
相違点3-1については、甲3-1発明と、甲4(特開2006-168344号公報)に記載された技術事項とに基づいて容易想到と認定された。相違点3-2については、甲3-1発明におけるPSA領域の個数を1つと特定することは、通常の技術的手段から当業者が容易に行い得ることにすぎないと認定された。これらにより、本件発明1の進歩性が否定された。
【裁判所の判断】(筆者注記:以下の下線部は、本事案における重要部分)
2 取消事由3(相違点3-1についての判断の誤り・無効理由4関係)について
(1) 甲3の記載 省略
(2) 甲4の記載 省略
(3) 前記(2)の記載によると、甲4の「スクリーン保護膜30」が本件発明1の「保護シート」に相当し、「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」がそれぞれ本件発明1の「第2剥離部」及び「第1剥離部」に相当することは明らかである。そして、甲4の「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」は、それぞれ「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」から、「スクリーン保護膜30」の外側に延びるように設けられ、「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」を剥がす際に手で持つ部分であるから(段落【0025】、【0026】、【図4】~【図6】)、いずれも本件発明1の「延出部」に相当するといえる。
ここで、甲4において「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」を設けたのは、手で「第一の突起部343」又は「第二の突起部344」を持って、それぞれ「第一の離型膜341」又は「第二の離型膜342」を便利に剥がせるようにするためである(段落【0025】)。そうすると、甲4に記載された発明とその属する技術分野を同じくする甲3-1発明(その内容は、前記第2の3(2)ア(ア)のとおり)においても、そのような利便性を図るため、甲4に記載された「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」の構成を適用して本件発明1の「延出部」を設けることは、本件優先日当時の当業者において容易に想到し得たことであると認められる。
(4) この点に関し、原告は、甲3-1発明に甲4に記載された「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」の構成を適用することには、阻害要因がある旨主張するが、以下のとおり、これを採用することはできない。
ア 原告は、まず、甲3-1発明はその貼付の対象として超大型のディスプレイパネル(最低でも17インチのものであり、適するのは82インチのものであり、更にそれより大きいものを含む。)を想定しており、その貼付を行うのは専門の技術者であるから、本件発明1の「延出部」のような部材は不要である旨主張する。
そこで検討するに、前記(1)のとおり、甲3には、甲3-1発明の光学フィルムを貼付する対象が「大型ディスプレイパネル」であり、「大型」とは17インチから82インチ程度までのものをいう旨の記載がある(前記(1)イ、ケ等)。また、特許請求の範囲においては、保護フィルムの貼付の対象となる大型ディスプレイパネルが少なくとも17インチのものである旨の特定がされている(前記(1)ツ)。さらに、実施例1においては、甲3-1発明の光学フィルムは40インチの大型液晶テレビに貼付され、実施例2においては、甲3-1発明の光学フィルムは23インチのコンピュータディスプレイに貼付されている(前記(1)ソ及びタ)。これら甲3全体の記載を参酌すると、甲3の「要約」に、「この方法は、対角線208cm(82インチ)の可視領域を有するような大型ディスプレイパネルでの使用に適している。」との記載があること(前記(1)ア)を考慮しても、甲3-1発明が82インチ程度の大型ディスプレイパネルのみをその貼付の対象としていると認めることはできず、甲3-1発明は、幅広い大きさの範囲(17インチないし82インチ程度)のディスプレイパネルをその貼付の対象とするものであると認めるのが相当である。そして、17インチ程度の大きさのディスプレイパネルに光学フィルムを貼付することが専門の技術者でなければ行えないとみるべき事情もない。そうすると、甲3-1発明の光学フィルムの貼付については、専門の技術者がこれを行うことを常に想定しているということはできないから、原告の上記主張は、その前提を欠くものとして失当である(なお、原告が主張する「把持部」(本件発明1の「延出部」に相当する部材)は、甲4における「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」を剥がすのに便利な「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」と同様の機能を有するものであるところ(甲4の段落【0025】等参照)、甲4の「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」は、甲3―1発明の分離剥離ライナーである「第1の部分38a」及び「第2の部分38b」に対応するものである。専門の技術者であったとしても、分離剥離ライナーを剥がすために「把持部」を設けることは便利となるものであって、仮に、甲3-1発明の光学フィルムがその貼付を専門の技術者が行うことを想定しているとしても、そのことから直ちに、甲3-1発明の光学フィルムにおいて、分離剥離ライナーである「第1の部分38a」及び「第2の部分38b」を剥がすのに便利な「把持部」を設けることが不要になるわけではない。)。
(中略)
エ なお、原告は、実験報告書(甲28の3、甲36)を根拠に、甲3-1発明の光学フィルムを巨大なディスプレイパネルに貼付する場合、「把持部」があると、かえって作業に支障を来す旨主張する。
しかしながら、上記実験において用いられたのは、82インチの光学フィルムのみであるところ、前記アのとおり、甲3-1発明は、常に82インチ程度の光学フィルムであることを前提としているわけではないから、82インチよりも小さいサイズの光学フィルムを用いた実験を省略する上記実験は、17インチないし82インチ程度といった幅広い大きさの範囲でディスプレイパネルに貼付することを前提とする甲3-1発明の光学フィルムに「把持部」を設けることの不都合さを示す実験としては、十分なものではない。加えて、23インチのディスプレイパネル及び82インチのディスプレイパネルに貼付することのできる2種類の光学フィルムを用いた被告の実験結果(「延出部」を設けても貼付作業に支障を来さず、むしろ有用であったとするもの。乙1、2)にも照らすと、原告の上記実験結果によっても、甲3-1発明の光学フィルムに「把持部」を設けると貼付作業に支障を来すことになると認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
3 取消事由4(相違点3-2についての判断の誤り・無効理由4関係)について
次いで、取消事由4について検討する。
(1)ア 原告は、甲3-1発明の光学フィルムは超大型のディスプレイパネル(最低でも17インチのものであり、適するのは82インチのものであり、更にそれより大きいものを含む。)に貼り付けられることを想定しているところ、そのような光学フィルムは、必然的に巨大なものとなり、これを対象面に仮止めするとなると、仮止部が1つでは作業ができないから、甲3-1発明の「PSA領域39」を「1箇所」にすると、甲3-1発明は、発明として機能しないことになる旨主張する。
しかしながら、前記2(4)アにおいて説示したとおり、甲3によっても、甲3-1発明が82インチ程度の大型ディスプレイパネルのみをその貼付の対象としていると認めることはできず、甲3-1発明は、幅広い大きさの範囲(17インチないし82インチ程度)のディスプレイパネルをその貼付の対象とするものであるから、甲3-1発明の光学フィルムが超大型のディスプレイパネルに貼付されるものであることを前提として、その「PSA領域39」を「1箇所」にすることが不可能であるということはできない(そもそも、「PSA領域39」を「1箇所」にするというときの「1箇所」とは、「PSA領域39」が設けられている場所の個数のみを示す概念であって、「PSA領域39」の大きさその他の属性について言及するものではないから、「PSA領域39」の個数が「1箇所」であることは、「PSA領域39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味しない。)。なお、甲3-1発明の光学フィルムが17インチ程度の大きさのディスプレイパネルに貼付される場合に、その「PSA領域39」を「1箇所」にすることが不可能であるとみるべき事情はない。
(中略)
イ 原告は、甲3には「PSA領域39」の全てにつき、「regions」と複数形が用いられており、図面にも「PSA領域39」が4箇所であることが示されているから、甲3―1発明の「PSA領域39」は4箇所又は複数箇所存在するものであり、これを「1箇所」にすることはできない旨主張する。
確かに、甲3において、例えば「剥離ライナー」については、「one or more release liners」などの語が用いられているのに対し、「PSA領域39」については、「regions」という複数形のみが一貫して用いられており、これに加え、図6等の図示(「PSA領域39」が4箇所に設けられている。)も併せ考慮すると、甲3-1発明は、「PSA領域39」を複数設けることを想定しているものと認められる。しかしながら、甲3には、「PSA領域39」を1箇所ではなく複数箇所に設けることの技術的意義について何らの記載もなく、「PSA領域39」の機能(「第2の部分30b」をディスプレイパネルに接着することにより、「第1の部分38a」を除去し、「接着剤層」をディスプレイパネルに接触させるなどする作業の間、「第2の部分30b」が容易に移動しないようにすること(前記2(1)シ))にも照らすと、「PSA領域39」を複数箇所に設けることが甲3-1発明の必須の構成であるということはできない。したがって、原告の上記主張は、結論において誤りである。
ウ 以上のとおりであるから、甲3-1発明の「PSA領域39」を「1箇所」にすることにつき、阻害要因はないと認めるのが相当である。
(2) 上記(1)イにおいて説示したところによると、甲3-1発明の「PSA領域39」を複数箇所に設けることにつき特段の技術的意義があるとは認められない。また、「PSA領域39」の機能は、上記(1)イのとおりであるところ、上記(1)アのとおり、「PSA領域39」の個数が「1箇所」であることは、「PSA領域39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を「PSA領域39」に付与することができるものと考えられる。そうすると、幅広い大きさの範囲(17インチないし82インチ程度)のディスプレイパネルをその貼付の対象とする甲3-1発明の光学フィルムにおいて、「PSA領域39」の個数を幾つにするかは、「積層体30」の材質、大きさ、重さ、硬さ、「PSA領域39」の材質、大きさ等の諸般の考慮要素を調節し、当業者において適宜選択し得る設計的事項であるということができる。したがって、本件優先日当時の当業者は、甲3-1発明の「PSA領域39」を「1箇所」とすることに容易に想到し得たものと認めるのが相当である。
(3) この点に関し、原告は、甲3-1発明において「PSA領域39」を「1箇所」とすることは設計的事項ではなく、本件発明1のように「仮止部」を「1箇所」とすることには、技術的意義がある旨主張する。
しかしながら、本件明細書において、「仮止部」を「1箇所」にすることの技術的意義について述べた部分はなく、かえって、本件明細書には、「前記第1実施形態においては、仮止貼付部30を第1剥離部21の1箇所に設ける構成としたが、これに制限されない。仮止貼付部30を第1剥離部21に加えて第2剥離部22にも設けてもよい。」との記載(段落【0100】)もみられるところであるから、本件発明1の「仮止部」を「1箇所」にすることにつき格別の技術的意義があるということはできない。原告の上記主張を採用することはできない。
(中略)
5 結論
以上の次第であり、取消事由3及び4はいずれも理由がないから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。
【所感】
裁判所の判断どおり、甲3-1において、フィルムの貼付対象である「大型ディスプレイパネル」の大きさが、82インチ程度に限定されるようには読み取れない。原告は、甲3-1のフィルムの貼付対象の大きさが82インチ程度であることを前提として阻害要因を主張しており、無理筋であったと感じる。
仮止部については、本件明細書の段落0038,0039に、その位置やサイズが詳細に記載されている。仮止部をそのサイズや位置とすることへの意義(例えば、仮止部を中心として回転方向に微調整が可能)が記載されていれば、それ自体が進歩性判断において有利に働いただけでなく、その効果の記載に基づいて、本願発明1を、仮止部とPSA領域との差異がより明確となるように訂正するという選択肢も生じたと考えられる